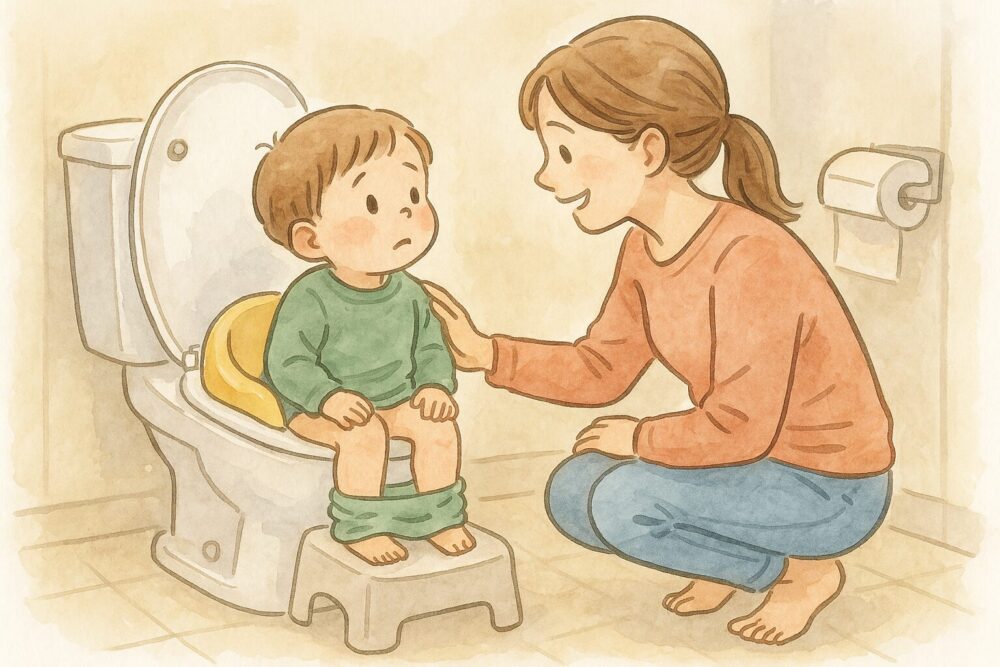
はじめに
「オムツが外れないまま入園しそうで焦っている」
「何度もチャレンジしては失敗、親も疲れてしまった」
そんな“トイレトレーニングが進まない”悩みに直面しているご家庭へ。
この記事では、作業療法士の視点から、トイトレがうまくいかない背景や、家庭でできる支援の工夫を年齢別・発達特性別にわかりやすくまとめました。実体験とともに、今すぐ使えるヒントを紹介します。
トイレトレーニングが進まない理由

身体機能の未成熟
排泄には、膀胱や腸の発達、自律神経の安定が関わります。これが整うタイミングは個人差があり、2歳で取れる子もいれば、4歳ごろまでオムツを使っている子も。
感覚の過敏さ・鈍さ
- おしっこの“ムズムズ”に気づけない(感覚鈍麻)
- トイレのにおいや音が怖い(感覚過敏)
- 便意を“嫌なもの”と感じて我慢してしまう
心理的な不安や成功体験の少なさ
過去の失敗体験(漏らした、怒られた)が不安や恐怖として残ることも。特に敏感な子は、安心してチャレンジできる“場づくり”が重要です。
年齢別に見るトイトレの特徴とつまずきポイント
| 年齢 | よくある様子 | 支援のヒント |
|---|---|---|
| 1歳半〜2歳 | おまるに興味を持ち始める 遊び感覚で座りたがることも | 絵本やぬいぐるみでトイレごっこからスタート 成功体験より「慣れる」ことが目標 |
| 2〜3歳 | イヤイヤ期で拒否が強くなる タイミングが合わず失敗しやすい | 「できなくても大丈夫」の安心感を伝える声かけ 短時間でチャレンジして、無理せず継続 |
| 3〜4歳 | 周囲と比べて焦りがち 成功と失敗が交互にくる | 日内リズムを観察し、トイレに座る時間を決める 経験を積み重ねて“自信”につなげる |
| 4〜5歳 | 夜のおむつが外れない “恥ずかしい”という感情が芽生える | 夜間排泄の記録でタイミングを把握 プレッシャーを与えず、続けやすい環境づくり |
作業療法士として伝えたい家庭での支援ポイント
1. 環境の見直し
- 座って安定できる補助便座+踏み台
- 明るく清潔な空間にし、怖くない場所に
- トイレに好きなキャラのステッカーや音楽を用意
2. 生活リズムとの連携
- 食後・起床後など“出やすいタイミング”を把握
- 1日2回だけでもOK!ルーティン化を目指す
3. できたことに注目する
- 「出なかったけど座れたね!」をしっかり褒める
- カレンダーに“トイレ座れたシール”など視覚的な達成感
発達特性がある子への配慮(ASD・ADHD傾向など)
- 見通しのなさ(いつ終わる?)が大きな不安に
- 感覚の強さ(におい・音・触覚)が刺激になりやすい
- 同じ便座でなければNGな“こだわり”も
→ 「いつ」「どこで」「どうやるか」を見える化する支援が有効です。写真スケジュールやタイマーなども効果的。
よくあるNG対応とOK対応
「また失敗?」「なんでできないの?」
そんな言葉、つい言ってしまったことはありませんか?
トイレトレーニング中は、思うように進まない場面も多く、親としても焦ったりイライラしてしまいがち。
でも、ちょっとした声かけや関わり方を変えるだけで、子どもは驚くほど前向きになれることがあります。
ここでは、ついやってしまいがちなNG対応と、代わりに試したいOK対応を場面別にまとめました。
「失敗したからこそ、次にどう関わるか」がとても大事。
一緒に、親子にとって心地いい関わり方を見つけていきましょう。
| シーン | NG例 | OK例 |
|---|---|---|
| 失敗後 | 「なんでまた漏らしたの!?」 | 「おしっこ出てたね。次また一緒にやってみようね」 |
| 長時間座らせる | 「出るまで出ないとダメ!」 | 「今日は2分だけ座ってみよう」 |
| 周囲と比較する | 「○○ちゃんはもう取れてるのに」 | 「○○は○○のペースで大丈夫」 |
トイトレに役立つおすすめアイテム比較表
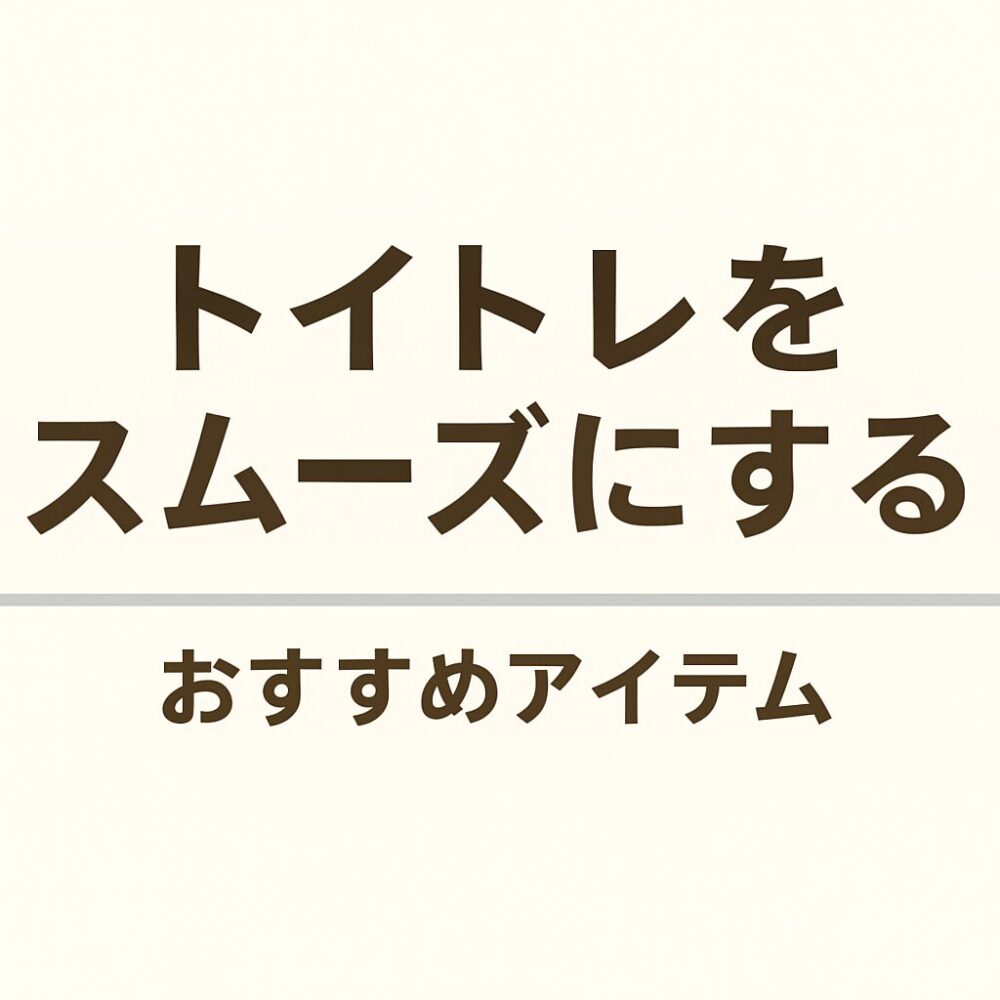
トイトレをスムーズにするおすすめアイテム
「何度言っても座ってくれない…」「失敗ばかりで、親のほうが心折れそう」
そんなトイレトレーニングの悩み、ありませんか?
子どもにとって“トイレに行く”ことは、大人が思う以上にハードルが高いもの。
だからこそ、無理に頑張らせるのではなく、少しだけ環境を整えてあげることがとても大切です。
ここでは、私自身の体験や支援の中で「これはあってよかった!」と思えた
トイトレをサポートしてくれるおすすめグッズを紹介します。
親子で楽しく、少しでもラクに進めるためのヒントになればうれしいです。
| 商品名 | 特徴 | 向いている子 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 補助便座(キャラ付) | 座るのが楽しくなる | トイレを怖がる子 | 約1,000円〜 |
| 踏み台 | 安定して座れる | 姿勢が不安定な子 | 約1,500円〜 |
| ごほうびシール | 成功を視覚化できる | 自信がつきにくい子 | 約500円〜 |
| トイレ絵本 | ストーリーで見通しが持てる | 初めてのトイトレ期 | 約1,000円〜 |
アイテム別の補足レビュー
補助便座(キャラ付き):
「大人用のトイレは怖い…」という子でも、好きなキャラクターがいるだけで、気持ちが切り替わることがあります。特に“最初の一歩”をサポートしたいご家庭におすすめです。
踏み台:
足が床につかないと、子どもは不安定で落ち着きません。踏み台があるだけで安心感が増し、排泄の感覚をつかみやすくなります。洗面所などでも兼用できます。
ごほうびシール:
「できたね!」の成功を目に見える形にするだけで、子どものやる気がぐんとアップ。完璧じゃなくても「がんばったこと」を認めてあげられるアイテムです。
トイレ絵本:
初めてのトイレで戸惑う子に、絵本を通して自然に「流れ」や「見通し」を伝えられます。ストーリーに感情移入することで、トイトレが前向きな経験になります。
気になったアイテムはこちらからチェック
使ってみて「これはうちの子に合ってた!」と感じることもよくあります。
まずは見てみるだけでもOK。無理なく、親子に合う選択肢を探してみてください
実体験|座れたのは“補助便座を変えてから”でした
わが家の息子は、最初トイレに座ることすら嫌がっていました。
実際に補助便座を買ってみたものの、“硬くて冷たい感じが嫌だったみたい”で、便座を見るだけで逃げてしまう日々…。
それでも、「まずはトイレに入るだけでOK」として1日1回だけチャレンジすることを続けていました。
最初にトイレに“座ってくれた”のは、開始してから12日目。
きっかけは、キャラクター付きのふかふか素材の補助便座に変えたことでした。
購入したのは【アンパンマンの補助便座(持ち手付き)】
持ち手がついていたことで「安心感がある」「乗り物っぽい」と気に入ってくれて、急に自分から「座ってみる」と言ってくれました。
そこからは、一気に進むわけではなくても、毎日“座る”→“出なくてもOK”→“出たら褒める”の流れを意識しながら、少しずつ成功体験を重ねられました。
親として焦る気持ちもありましたが、「子どものペースを信じること」「失敗しても笑顔で関わること」が、結果的にいちばんの近道だったと今では思います。
夜のオムツはずしや便秘について
夜間の排尿コントロールは、日中より時間がかかります。
- 膀胱容量の発達
- 寝ている間の感覚の鈍さ
→ 4〜5歳ごろまで残る子も多いので、焦らず対応を。
また、便秘がトイレ嫌いの原因になることも。
- 食事の見直し(食物繊維・水分)
- 排便リズムの記録
- 小児科での相談も視野に
→ 排便・排尿ともに、「成功=できた!」という体験の積み重ねがカギです。
よくある質問(FAQ)
Q. 4歳過ぎてもオムツが取れません。異常でしょうか?
→ 発達には個人差が大きく、4歳後半で完了する子も多くいます。不安な場合は小児科や保健師へ相談を。
Q. 保育園ではできるのに家ではやりません
→ 園では“流れに乗って”できているだけで、家では安心して“本音”が出やすいものです。
Q. 発達が遅れてるかもと感じたら?
→ 行政の相談窓口や療育センターの利用を検討しつつ、将来への備えとして「保険の見直し」を考えるご家庭も増えています。
まとめ|トイレは「自立の第一歩」。だからこそ焦らず育てたい
トイトレは単なる排泄習慣ではなく、自分の身体を感じる・意思を伝える・生活を整えるという“生きる力”の始まりです。
焦らず、子ども一人ひとりのペースで。
できたときには一緒に喜び、うまくいかないときは寄り添う。
それが、長い育児の中での“信頼”にもつながっていくはずです。
関連記事・あわせて読みたい
- 着替えがうまくできない子への支援
- お風呂が苦手な子への支援
- 歯みがきを嫌がる子への支援
- ライフステージ別 保険の見直しガイド|わが家の体験から学んだ“いま必要な備え”
- 発達グレーの子どもに多い“よくある悩み”と家庭でできる対応まとめ
はじめてこのブログに来てくださった方へ
このブログでは、
子育て・夫婦のライフプラン・保険の見直し・仕事、生活に役立つグッズなど、
暮らしの中で「ちょっと気になってきたこと」を、やさしく整理してお届けしています。
結婚、出産、育児、そしてこれからの備え――
「わが家に必要なこと」を一緒に考えたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
