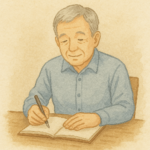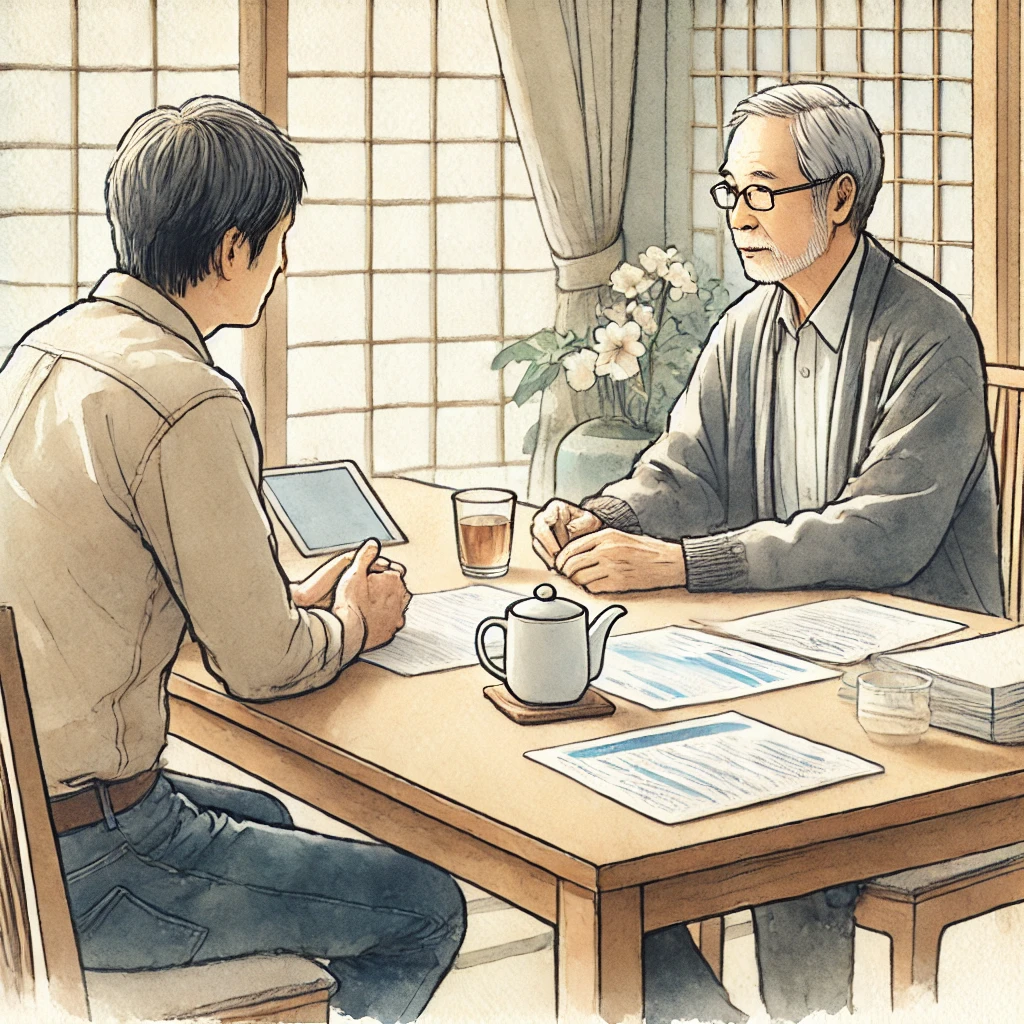
はじめに

「終活って、なんだか怖い言葉だよね」
そうつぶやいたのは、私の祖母でした。
数年前、祖父が入院したのをきっかけに、家族で“もしも”の話をすることに。
でも、いざ話そうとすると何から手をつけていいのかわからず、戸惑ってしまったのを今でも覚えています。
終活は、亡くなる準備ではありません。
「これからを、自分らしく、家族と笑顔で過ごすため」の準備なんです。
この記事では、終活初心者でも取り組みやすい5つのステップを、私自身の家族の経験も交えながらご紹介します。
「祖父母にどう話せばいいか分からない」という方にもきっとヒントになりますよ。
ステップ1:祖父母と始めるエンディングノートの書き方
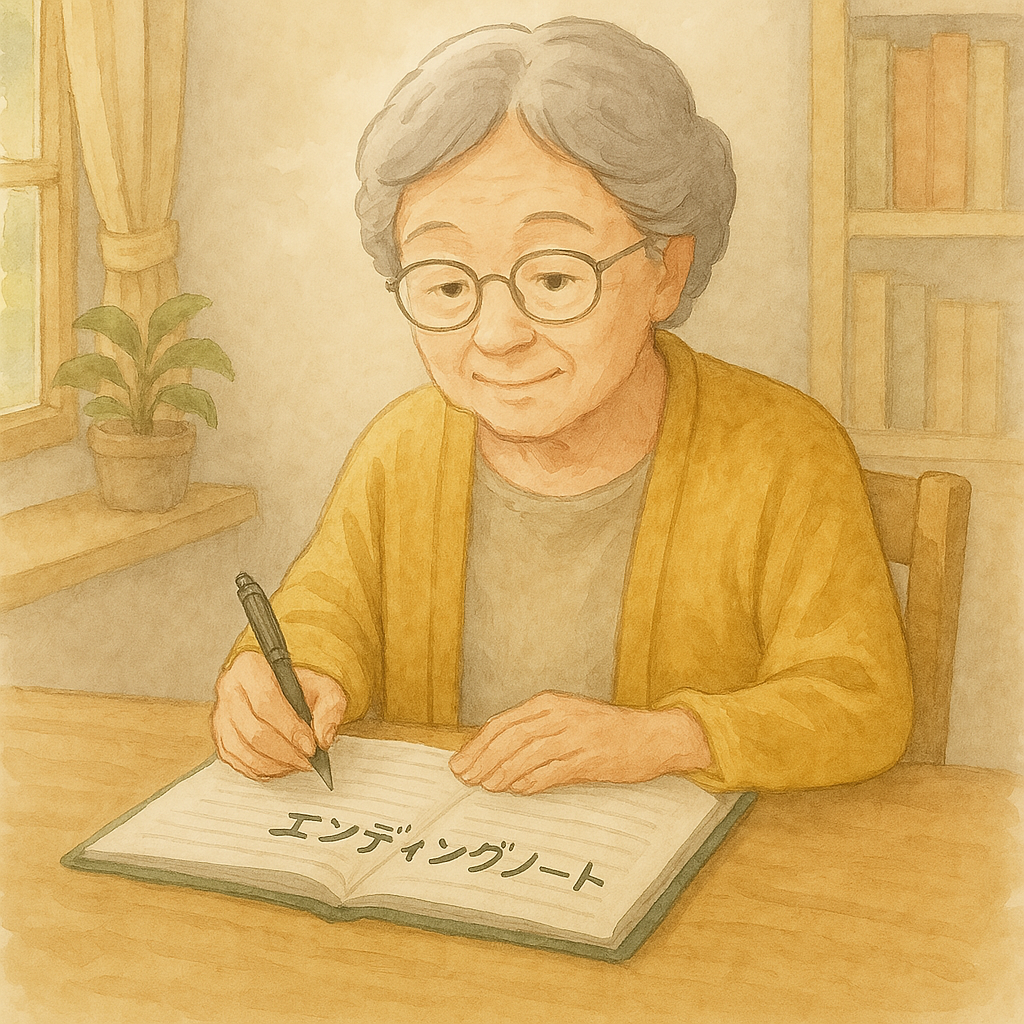
自分の気持ちや希望を“見える化”できる第一歩。
うちの祖母が最初に取り組んだのが、エンディングノートでした。
「こんなの恥ずかしいよ〜」なんて言いながらも、好きな食べ物や思い出を書き始めると、不思議と笑顔に。
最初は難しく考えなくて大丈夫。
「名前・住所・連絡先・趣味」などから始めるだけでも立派な一歩です。
書店で手に入るもののほか、無料でダウンロードできるテンプレートもあるので、気軽に始められます。
ステップ2:祖父母と一緒に進める生前整理のコツ
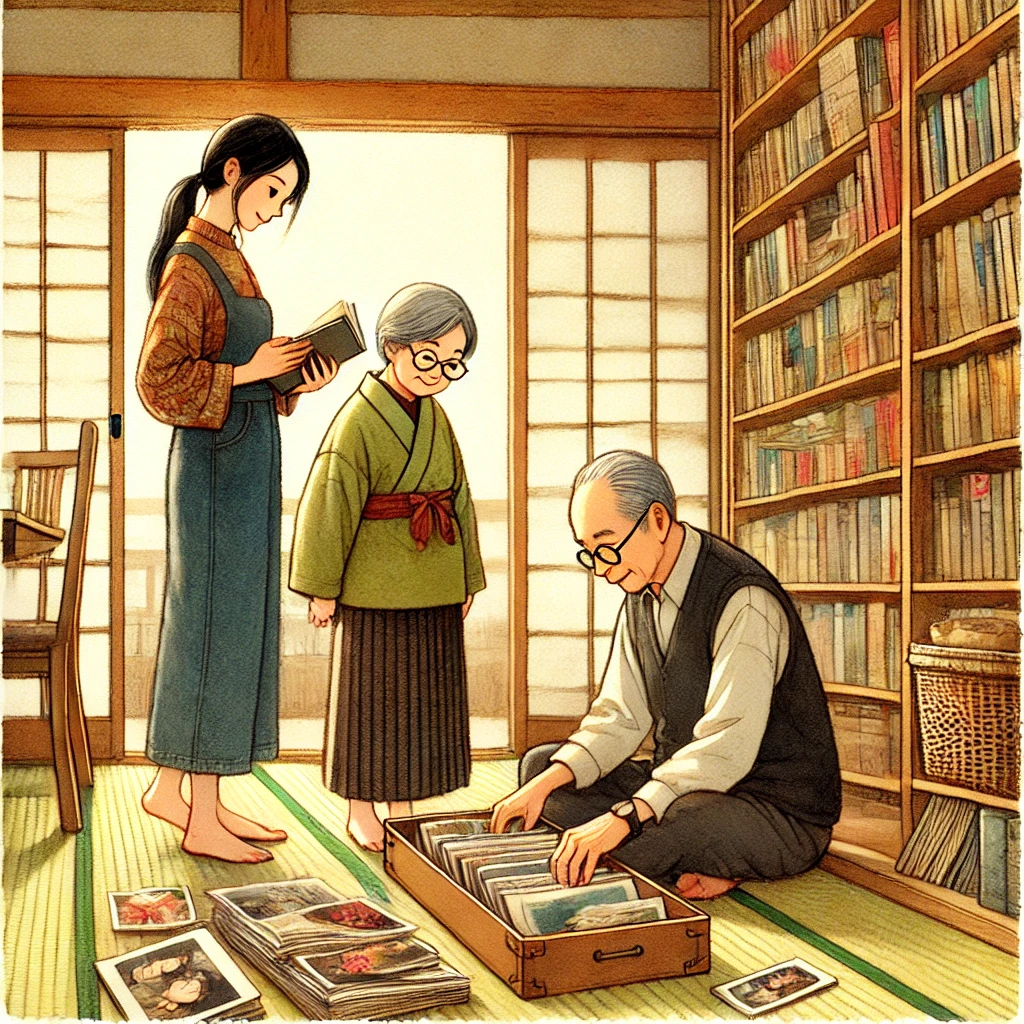
思い出の品を見返しながら、感謝を伝える時間に。
ある日、祖父が「これはもういらないか」と古い手紙を処分しようとしていました。
でも中身を見てみると、祖母が若い頃に送ったラブレターだったんです。
「捨てる前に見てよかったね」と家族で大笑い。
そんな風に、生前整理は単なる“片付け”ではなく、家族の時間や思い出を再発見する時間でもあるんです。
書類や思い出の品を少しずつ見直すことで、家族との会話のきっかけにもなります。
ステップ3:医療・介護についての話をゆっくりと
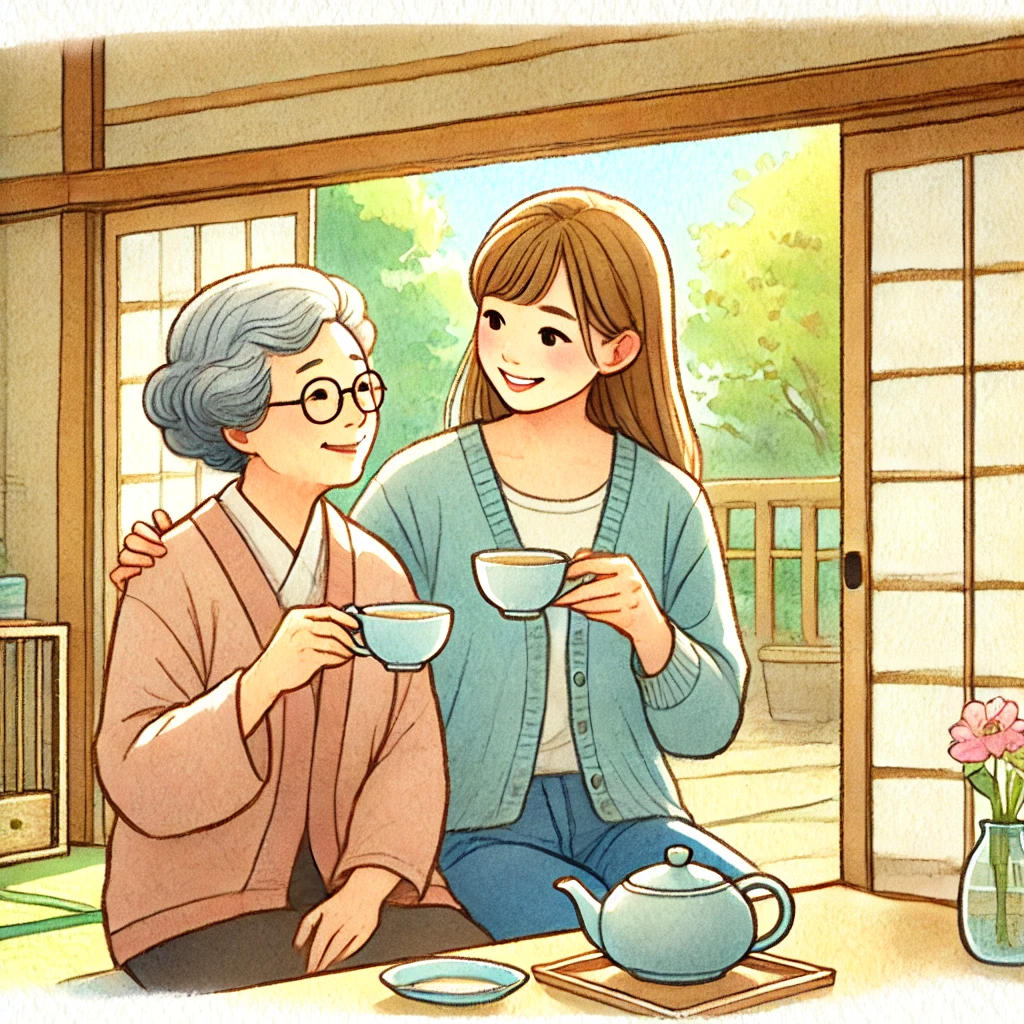
「延命治療をするかどうか」は、元気なうちにこそ話すべきこと。
祖父が入院した際、医師から「人工呼吸器をつけますか?」と聞かれて、家族が戸惑った経験があります。
本人の希望が分からず、結局家族で悩んで決めることに…。
その後、祖母とは「延命治療どう思う?」と話し合うようになりました。
事前指示書(ACP)を使って、少しずつ自分の思いを共有できたのが大きな安心につながりました。
無理に重い話をする必要はありません。
「もしものとき、どんなふうに過ごしたい?」といった、ゆるやかな問いかけから始めてみてください。
ステップ4:お金と相続を“今”見直す

「知らなかった」では済まされない、大事なお金の話。
祖母がよく言っていたのが、「お金のことは亡くなってからわかればいいと思ってた」。
でも、実際はそうはいきませんでした。
通帳の場所が分からない、保険に何があるのかわからない…といったことが、家族にとって大きな負担に。
終活では、
- 預貯金や保険の把握
- 不動産などの名義チェック
- 簡単な遺言書の準備
が重要になってきます。
また、成年後見制度や家族信託といった制度についても、簡単に知っておくだけで安心材料に。
ステップ5:やりたいことリストを一緒に作る
終活は、夢を叶えるチャンスでもある。
「死ぬ準備なんてイヤよ」と言っていた祖母が、一番楽しそうに取り組んだのが「やりたいことリスト」でした。
- 孫と温泉旅行に行きたい
- 昔住んでた街をもう一度歩いてみたい
- 昔のレシピで料理をふるまいたい
そんな小さな夢を、家族と一緒に叶えていく時間は、とてもあたたかく、記憶に残るものでした。
「前向きな終活」は、笑顔の時間を増やすヒントにもなります。
まとめ
終活とは、「死に備える」のではなく、「今を大切に生きるため」の準備です。
すべてを一気にやろうとしなくても大丈夫。
まずは「エンディングノートを書く」など、小さな一歩から始めてみませんか?
祖父母と話すことで、不安が安心に変わっていくのをきっと感じられます。
「まだ元気な今こそ」が、終活のはじめどきです。
次の記事はこちらから