
「外で遊ぼう」と言うと、泣いてしまうわが子を見て…
他の子は公園で元気に走り回っているのに、
うちの子は外に出ようとするだけで不機嫌――。
「発達に問題があるのかな」「このままでいいんだろうか」と、
不安を感じたことはありませんか?
実は、外遊びを嫌がる子には感覚・運動・人との関わり方など、
発達の特徴が関係していることがあります。
この記事では、子どもの発達支援に携わる作業療法士のパパが、
外遊びを苦手とする子どもの特徴と、親ができる関わり方をお伝えします。
あなたのお子さんはどうですか?外遊びが苦手な子の特徴チェック
以下のような様子、当てはまるものはありますか?
- 砂や土を触るのを嫌がる
- 公園に行こうとすると泣く・逃げる
- バランスをとるのが苦手でよく転ぶ
- 他の子どもが近づくと緊張して固まる
- 遊具に登るのを怖がる
- 風や音に過敏に反応する
- 外遊びに誘っても「やだ」と言ってすぐ帰りたがる
これらは、感覚過敏・運動への不安・対人不安などのサインかもしれません。
外遊びが苦手な子に多い3つの背景
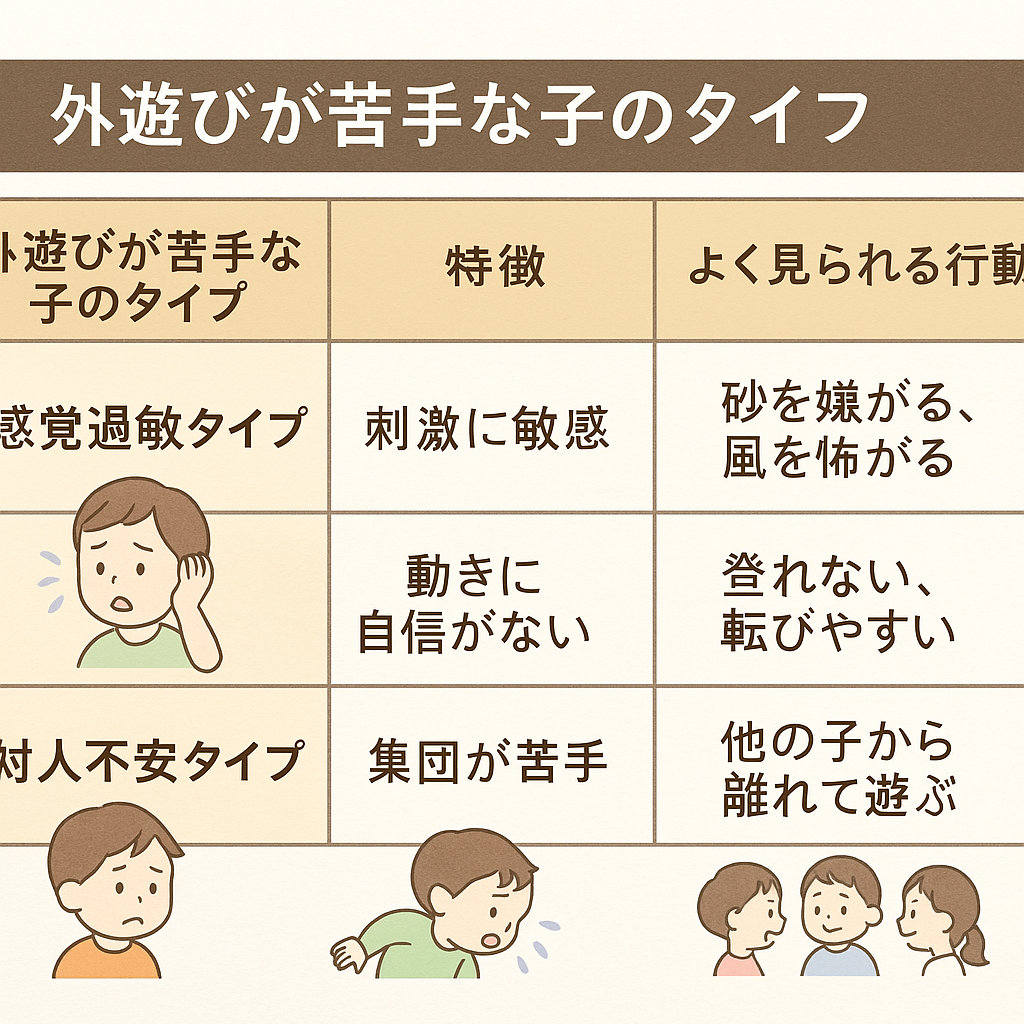
1.感覚が敏感すぎる(感覚過敏)
- 砂のザラザラが「痛い」と感じる
- 外の音や風にびっくりしやすい
- 足が汚れるのがどうしてもイヤ
こうした子にとって、外は“刺激が強すぎる場所”。
無理に出そうとすると、強い拒否反応が出てしまうことがあります。
2.運動が苦手で自信がない
- よじ登りやジャンプが苦手
- 体幹やバランスの発達がまだ未熟
- 「できない」「怖い」と思いやすい
運動面で苦手意識があると、外遊びが“つらい場所”に。
うまくいかない経験の繰り返しは、自信の低下にもつながります。
3.人との関わりに不安がある
- 知らない子がいると近づけない
- 声をかけられると固まってしまう
- 集団が苦手で一人遊びを好む
こうした子は、外遊び=人に関わらなきゃいけない場所と感じてしまい、自然と距離をとる傾向があります。
無理に外で遊ばせなくてもいいんです
私も正直、最初は「なんで公園で遊んでくれないんだろう」って悩みました。
周りの子と比べてしまって、
イライラしたり、不安になったりすることもあって…。
でも、あるときふと気づいたんです。
「この子にはこの子の“今できる形”がある」って。
それからは、「外遊び=正解」じゃなく、
“その子にとって心地よい関わり方”を一緒に探そうって考えるようになりました。
作業療法士パパが考える、やさしい外遊びの工夫
1.まずは安心できる外の環境をつくる
- ベランダ、玄関先、家の前など
- 人が少ない時間帯に出る
- 音や風を遮れる服装(フードや帽子など)
“安全基地”を外にもつくることが第一歩になります。
2.感覚刺激は“調整できる形”で
- 砂遊び → 水を加えてやわらかく
- 手が汚れる → 手袋やスコップを使う
- 地面に座れない → レジャーシートを敷く
「触らないといけない」ではなく、「どうすればできそう?」と選択肢を増やすのがポイントです。
3.運動が苦手なら、室内で“できた!”を増やす
- クッション渡り・トンネルくぐり
- 布団山ジャンプ・バスタオルそり
- バランス遊びで体幹を育てる
外遊びにこだわらず、まずは動きの“土台づくり”を室内で楽しく。
4.わが家の“ちょこっと外遊び”実例
- 郵便ポストまでのお散歩
- 葉っぱや石を拾って観察
- ベランダでシャボン玉タイム
「長時間」「がっつり」じゃなくていい。
「ちょっと外に出た」という経験だけでも、子どもにとっては大きな一歩です。
よくある質問Q&A
Q:外で全く遊ばないのは問題?
A:いいえ。その子にとって安心できる遊び方をすればOK。外に出なくても、室内での工夫で発達を支えることは十分可能です。
Q:感覚過敏って、病院に相談するべき?
A:日常生活に支障が出ている場合は、発達外来や療育機関に相談を。ちょっとした不安でも、相談することで親の気持ちもラクになります。
まとめ|その子らしい「できた」を一緒に見つけていこう
外遊びが苦手=ダメ、ではありません。
子どもはそれぞれ「今できること」が違うだけ。
親ができるのは、「その子に合った関わり方を一緒に探してあげること」です。
作業療法士としても、パパとしても――
外遊びを通して「楽しい!」と感じられる時間が、少しずつ増えていくように。
そんな関わりをこれからも続けていきたいと思っています。
