
こんな方におすすめです
- 子どもが「学校に行きたくない」と言い始めて不安になっている
- 登校しぶりが続き、どう支えたらいいか悩んでいる
- 学校とどう関わればよいか分からず戸惑っている
- 家庭でできることを知り、子どもを安心させたい
はじめに|「このままで大丈夫?」という不安に寄り添いたい
「今日、学校行きたくない」
朝の食卓で突然そう言った子どもの一言に、戸惑った経験はありませんか?
- たまたま疲れているだけだろうか?
- 友だちと何かあった?
- 毎日繰り返されたら、どうしよう…
親は焦りと不安で頭がいっぱいになります。
「まさか、うちの子が不登校になるなんて…」という戸惑い。
けれど実際には、不登校は誰にでも起こり得る身近な問題です。
文部科学省の調査によれば、令和4年度の不登校児童生徒数は過去最多の約29.9万人にのぼりました。
その多くは“登校しぶり”と呼ばれる軽微な兆候から始まっているとされます。
この記事では、子どもが学校を「行きたくない」と感じ始めたときに、親が家庭でできる具体的な5つの行動と、信頼できる学習支援や相談先の情報をまとめています。
誰にも相談できずに悩んでいるあなたの力になれたら幸いです。
この記事では「兆候に気づくこと」にフォーカスしていますが、
その後の対応(声かけや学びの支援)についても、別記事で詳しく紹介しています。
不登校の兆候とは?よくある“はじまりのサイン”
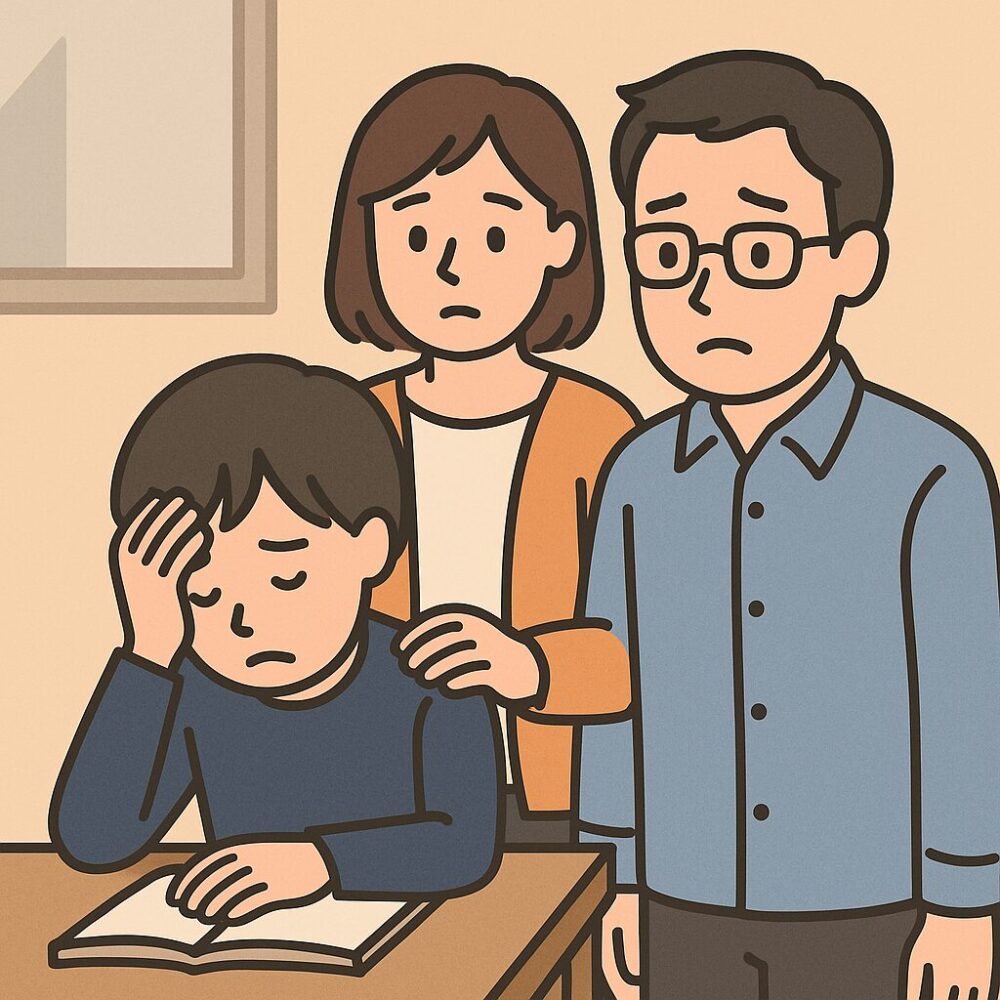
不登校は突然始まるわけではありません。
ほとんどの場合、子どもは何らかの「違和感」や「つらさ」を抱え、それを小さな行動の変化で表現しています。
よく見られる兆候
- 月曜日や休み明けに体調不良を訴える(頭痛、腹痛、吐き気など)
- 宿題・テストの話になると過敏に反応する
- 「なんとなくイヤ」と口にするが、理由は説明できない
- 朝起きるのが極端に遅くなる or 寝つきが悪くなる
- 表情が暗い、無口、甘えが強くなる
こうした兆候を「怠け」や「やる気がない」と判断してしまうと、子どもはさらに心を閉ざしてしまいます。
大切なのは、「行けない」ことを責めるのではなく、「どうしたの?」と安心して話せる環境を作ることです。
子どもが抱える“言葉にならないつらさ”
子どもは、自分の不安や葛藤を大人のように言語化することができません。
「なんとなくイヤ」という言葉の背景には、こんな想いが隠れているかもしれません。
- 「授業で当てられるのが怖い」
- 「友だちの輪にうまく入れない」
- 「怒られるのがつらい」
- 「学校にいると疲れてしまう」
- 「うまくやらなきゃいけないと思うとしんどい」
本人が理由をうまく言えないからといって、そのつらさが存在しないわけではありません。
むしろ、説明できないしんどさほど深刻であるケースも多くあります。
家庭でできる5つの支援|親の行動が子どもの安心をつくる

1. 「今日は休もうか」と一言、安心を渡す
無理に登校させるのではなく、「休んでもいいよ」と言ってもらえることが、子どもにとっては何よりの救いです。
「休む=逃げ」ではありません。
「心を整えるための時間」として、安心して立ち止まれる選択肢を持たせることが、結果的に前向きな行動へつながります。
2. 理由を聞き出すより“そばにいる”ことを優先する
親として「何があったの?」と聞きたくなるのは自然です。
でも、言葉にならない気持ちを無理に引き出そうとすると、かえって心を閉ざしてしまうことも。
- 一緒にごはんを食べる
- テレビを見ながらゆっくり過ごす
- 特に何も話さず、同じ空間にいる
これだけでも、子どもにとっては「ひとりじゃない」と感じられる支えになります。
3. 学校以外でも“学べる場”があると知る
「このまま学習が遅れたらどうしよう」
そんな不安を抱える親御さんも多いでしょう。
けれど、今は家庭で学べる選択肢が豊富にあります。
比較|不登校の子におすすめの学習サービス
| サービス名 | 特徴・メリット | 対象学年 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| すらら | ・無学年式で学習のつまずきまでさかのぼれる・アニメーション動画で学びやすい | 小学生〜高校生 | 学習の遅れに不安があり、自宅で一人で取り組みたい子 |
| 学研WILL学園 | ・通信制高校サポート校とフリースクールの機能を併せ持つ・少人数制、個別対応、在宅コースやメタバースキャンパスあり・進路相談や生活支援も充実 | 小学6年生〜高校生 | 学校に通うのが難しく、自分のペースで学びたい子将来の進路を一緒に考えたい子 |
| フリースクール | ・学習支援に加え、「居場所」としての役割も・活動内容や方針は地域によって異なる | 小学生〜高校生 | 学校に行くのがつらく、人とのつながりがほしい子 |
選び方のポイント
- 自宅で完結したいなら「すらら」
- 進学・復学も視野に入れるなら「学研WILLナビ」
- 居場所を大事にしたいなら「フリースクール」
どれも「今の子どもに合ったペースで学べる」ことが特徴です。
「やらせなきゃ」ではなく、「学ぶって楽しいかも」と思えるような導入が大切です。
4. 相談先を知っておくだけでも安心につながる
「どこに相談すればいいか分からない」という親はとても多いです。
でも、実は無料で相談できる公的機関が数多くあります。
主な相談先一覧
| 支援先 | 主な役割 | 利用方法 |
|---|---|---|
| 教育支援センター(適応指導教室) | 学校復帰支援+生活リズム支援 | 教育委員会に相談 |
| こども家庭支援センター | 家庭や発達、メンタル面の総合相談 | 市町村HPから連絡可 |
| スクールカウンセラー | 学校内での心理支援+関係機関との連携サポート | 学校経由で面談予約可能 |
「大ごとにしたくない」と思う気持ちもあると思います。
でも、親が孤立しないことは、子どもへの最大の支援でもあるのです。
5. 親自身が“がんばりすぎない”こと
子どもが不登校になると、親は自分を責めてしまいがちです。
- 「私の育て方が悪かったのかも」
- 「もっと早く気づけていれば…」
- 「周りの家庭はちゃんとやれているのに…」
そんなふうに思わなくていいのです。
あなたはすでに、子どもの異変に気づき、調べ、行動しようとしています。
それ自体が、子どもにとっては何よりの支えです。
よくある質問(Q&A)
Q. どのくらい休ませていいの?
「○日まで」と決める必要はありません。
子どもの様子を見ながら、少しずつ整えていく形で問題ありません。
学校にも「無理には行かせたくない」「本人の様子を見ながら考えたい」と伝えれば大丈夫です。
Q. 学校とのやり取りが不安です…
担任やスクールカウンセラーに、「今は本人の気持ちを優先したい」と伝えるだけでOK。
直接言いづらい場合は、カウンセラーや養護教諭経由でも相談できます。
Q. このまま不登校が長引いたらどうしよう?
現在は多様な進路があり、支援学校・通信制高校・フリースクール・オンラインスクールなど、
子どもに合った方法で進学・就職する道も十分開かれています。
焦らず、今できることから整えていきましょう。
親子の声|ある家庭の体験談
小5の娘が、「もう学校行きたくない」と泣き出した朝がありました。
理由は分からず戸惑いましたが、「じゃあ今日は休んでいいよ」と伝えたら、
安堵の表情を浮かべて、静かに横になりました。
数日間はほとんど会話もできませんでしたが、1週間後に「実は授業で…」と話してくれて。
今はオンライン教材で学びながら、月に1回フリースクールにも通っています。
「わかってくれるって思えたとき、安心した」と言われたのが忘れられません。
まとめ|「行けない」ではなく「今は止まっていい」

子どもが学校に行けなくなったとき、
それは“問題”ではなく“心の防衛反応”です。
- 無理に行かせないこと
- 家庭を安全基地にすること
- 親も自分を責めないこと
この3つを心に留めて、まずは今日を一緒に穏やかに過ごすことを目指してみてください。
不登校のサインに気づいたあと、どうすれば?
「もしかして…」と気づいたあとの対応は、とても大切です。
わが家では、声かけの仕方や家庭での学び方を見直すところから始めました。
▼ こちらの記事もぜひ読んでみてください:
当ブログの関連記事はこちらから
はじめてこのブログに来てくださった方へ
このブログでは、
子育て・夫婦のライフプラン・保険の見直し・仕事、生活に役立つグッズなど、
暮らしの中で「ちょっと気になってきたこと」を、やさしく整理してお届けしています。
結婚、出産、育児、そしてこれからの備え――
「わが家に必要なこと」を一緒に考えたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
