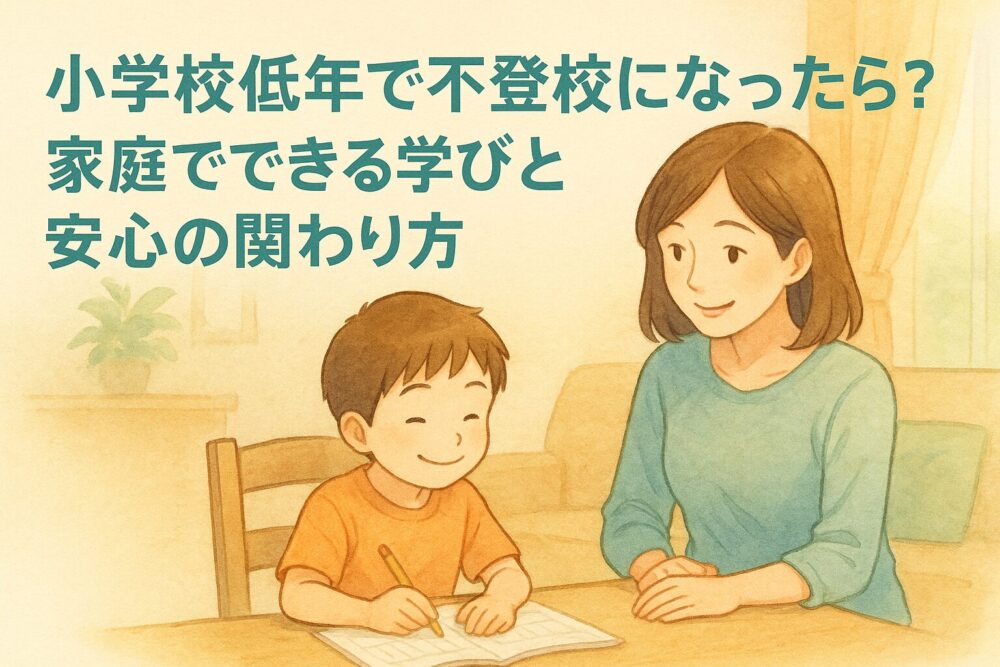
はじめに|「まさか、うちの子が…」と思ったとき
「小1になったばかりなのに、もう学校に行きたくないって…」
「勉強も始まったばかりなのに、遅れてしまったらどうしよう…」
そんな風に感じて、このページにたどり着いた方もいるかもしれません。
でも、まず最初に伝えたいのは「あなたは一人じゃない」ということ。
そして、小学校低学年での不登校は、“特別なこと”ではありません。
この記事はこんな人におすすめです
- 小1〜小3のお子さんが「学校に行きたくない」と言い出して戸惑っている方
- 「まだ小さいのに…」と将来への不安が大きくなっている方
- 登校を促すたびに泣かれて、どう関わっていいか分からなくなっている方
作業療法士として、不登校の子どもと関わってきて感じたこと
私は普段、発達や心の特性を持つ子どもたちの支援に関わる作業療法士として働いています。
その中で、「不登校=悪いこと」ではなく、「今、安心できる場所が必要な状態」なんだと、実感することがたくさんありました。
特に低学年の子どもたちは、まだ「自分の気持ちをことばで整理する力」が育っていない時期。
学校がしんどい理由も、本人がうまく言えないことがほとんどです。
だからこそ、無理に理由を探ったり、焦って登校を促すよりも、
「家を安心できる場所にすること」
「毎日の生活リズムを崩さずに過ごすこと」
この2つがとても大事だと、現場での経験から感じています。
小学校低学年の不登校は、特別なことじゃない
実際、小1〜小3の子どもが「学校に行きたくない」と言い出すことは、めずらしくありません。
入学後の環境変化、疲れ、緊張、人間関係…小さな心には負担がたくさんあります。
「行きたくない」は、「学校がイヤ」ではなく、
「ちょっとだけ休みたい」「疲れたから甘えたい」そんな気持ちの表れかもしれません。
親が不安になるのは当然。でも、その不安を子どもにそのままぶつけてしまうと、
「自分のせいでママが困ってる」「もっとがんばらなきゃ」と、プレッシャーに感じてしまうこともあります。
まずは、「そう思う日もあるよね」と受けとめることから始めてみましょう。
家庭でできるサポート①|生活リズムと安心できるルーティン
不登校が続くと、どうしても生活リズムが乱れがちになります。
朝起きられない、夜寝つけない、お昼にボーっとしてしまう…。
でも、子どもの心を落ち着かせるには、「何時に起きる」「ごはんを食べる」「お風呂に入る」など、毎日の決まった流れがとても大切です。
作業療法士として関わってきた中でも、“決まった時間に起きて、決まった場所で過ごす”だけで、子どもが安心し始めるケースはたくさんありました。
無理に学校に行かせなくても、まずは「家でリズムを整える」ことからはじめてみませんか?
- 朝はカーテンを開けて一緒にごはんを食べる
- 午前中は図鑑を読んだり、折り紙をしたり
- お昼を食べて、おやつタイムが終わったら少し外に出る
こうした「家の中でできる小さなルール」が、“子どもにとっての安心”につながります。
家庭でできるサポート②|「学び」より「関わり」を大事にする
親としては「勉強の遅れ、大丈夫かな?」と心配になりますよね。
でも、小学校低学年の時期に一番大切なのは、知識よりも“自信”や“安心感”です。
たとえば…
- 絵本の読み聞かせ
- 一緒にクッキーを焼く
- レゴやお店屋さんごっこでお金のやりとりをする
こうした関わりの中にも、自然な“学びの芽”はたくさんあります。
「一緒に過ごすだけで、子どもは少しずつ回復していく」──これは支援現場でも、家庭でも同じです。
家庭でできるサポート③|少しずつ“外の世界”とつながる練習を
ある程度家で落ち着けるようになったら、外の世界とのつながりを少しずつ取り戻していくのもおすすめです。
- 近所の公園に出かけて、少しだけ体を動かす
- 図書館に一緒に行って、好きな本を選んでもらう
- コンビニで「これ買ってきて」と簡単なおつかいを頼んでみる
重要なのは「目的をもたない外出」ではなく、子どもに“小さな成功体験”を積んでもらうことです。
「できた!」が増えると、子どもは少しずつ自分を信じられるようになっていきます。
無理に登校を促さなくても大丈夫|学び方はいろいろある
「学校に行かない=勉強できない」と思われがちですが、今は家庭で学べる方法がたくさんあります。
たとえば:
- タブレットやPCで使える無学年式教材(すらら・スタディサプリなど)
- 紙ベースのやさしいワーク(ポピー・Z会など)
- 好きなテーマだけを深掘りできる図鑑・YouTube・お絵かき教材
オンライン教材の中には、「今日できたこと」を毎日記録して褒めてくれる仕組みもあり、
子どもが自然と自信を持ちやすくなっています。
わが家も、「勉強させなきゃ」ではなく「遊びながら学べればいい」という気持ちで取り入れたところ、
子どもが自分から机に向かうようになりました。
おわりに|“いま”の子どもを信じることから
低学年で不登校になると、「このままずっと…」と不安になりますよね。
でも、今しかできない関わりが、きっとあとで子どもの“芯”になります。
- 家が安心できる場所であること
- 子どもが「大丈夫だよ」と言ってもらえること
- 小さな「できた!」を一緒に喜べること
それだけで、子どもは少しずつ、前を向く力を取り戻していきます。
焦らなくても、大丈夫です。
子どものペースで、今できることからはじめていきましょう。
関連記事もあわせて読む
はじめてこのブログに来てくださった方へ
このブログでは、
子育て・夫婦のライフプラン・保険の見直し・仕事、生活に役立つグッズなど、
暮らしの中で「ちょっと気になってきたこと」を、やさしく整理してお届けしています。
結婚、出産、育児、そしてこれからの備え――
「わが家に必要なこと」を一緒に考えたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
