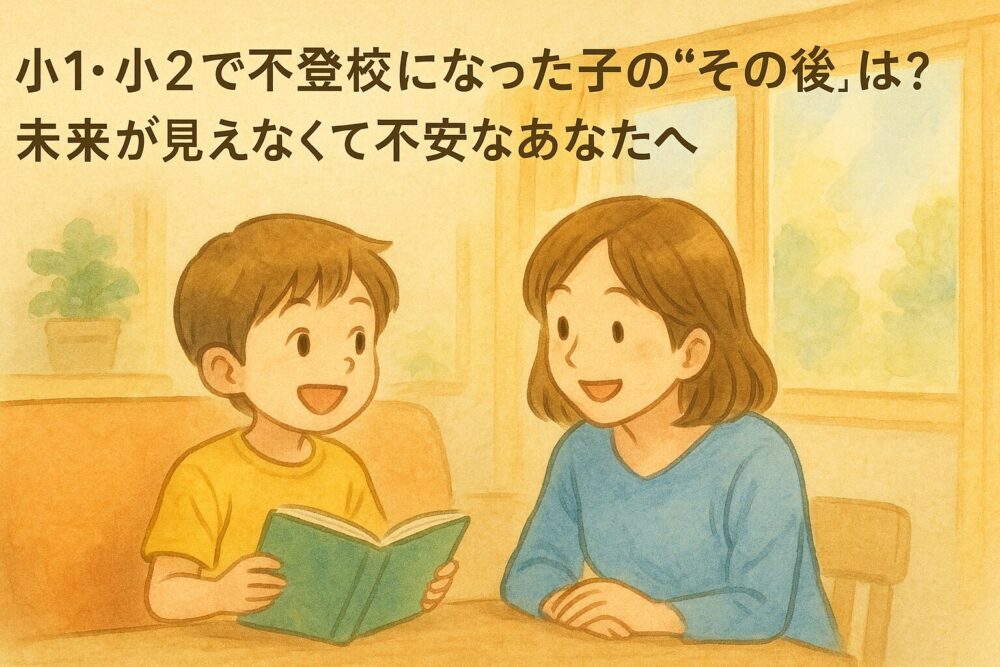
はじめに|「このままで大丈夫なの…?」と思ったときに
「また今日も学校に行けなかった…」
「小1なのに、このままで勉強についていけるのかな…」
「この子の将来ってどうなるんだろう…」
わが子が学校に行けない日が続くと、
親としては“今”だけじゃなく、“この先”がどんどん不安になっていきますよね。
私は作業療法士として、多くの不登校の子どもたちと出会ってきました。
そして、親御さんの中には「低学年での不登校=一生の遅れになる」と思い込んでしまう方も少なくありません。
でも実際は──
子どもは“安心できる経験”を積みながら、ゆっくりと自分のペースで育っていくものです。
この記事では、「低学年で不登校になった子の“その後”」について、
私が実際に見てきたケースや、わが家の小さな気づきを交えながらご紹介します。
この記事はこんな人におすすめです
- 小1〜小2のお子さんが不登校になり、このままでいいのか悩んでいる方
- 勉強の遅れ・社会性・将来のことが心配でたまらない方
- 「自分の関わり方、間違ってるのかな…」と不安になっている親御さん
- 他の家庭の“その後”の様子が知りたい方
不登校=ずっとこのまま…ではありません
「このまま引きこもりになったらどうしよう」
「将来、ちゃんと自立できるのかな?」
不登校が続くと、どうしても“最悪の未来”を想像してしまいますよね。
でも、私が出会ってきた子どもたちの多くは、
数ヶ月〜数年かけて、自分のタイミングで外の世界との関わりを再開していきました。
- ある子は、家庭でのんびり過ごしているうちに
→ 本が好きになって、図書館に通うように
→ 調べ学習から少しずつ「勉強って面白いかも」に - またある子は、登校せずに在宅で過ごす中で
→ タブレットで動画教材にハマり
→ 「これ、続けたいから毎日やる」と学習リズムが定着
“学校”という場に戻らなくても、子どもは自分のやり方で学び、自信を育てていくことができるんです。
低学年だからこそ「取り戻せる」力がある
小1〜小3は、“学力”よりも“基本的な生活と自己肯定感”を育てる時期です。
だからこそ、この時期に「焦って学校に戻す」よりも、
「安心して自分らしく過ごす経験」を積んだ方が、長い目で見るとプラスになることも多いです。
むしろ、ここで焦って失敗体験を重ねてしまうと、
「やっぱり自分はダメだ」と思い込んでしまうリスクもあります。
「いまの子どもを信じて、見守ること」──
これは、何よりも価値ある家庭での支援だと感じています。
小さな“できた”が自信を取り戻すきっかけに
不登校の子どもたちを見てきて感じるのは、
「成功体験」よりも「安心できる失敗体験」の方がずっと大事だということ。
たとえば…
- 料理中に卵を割ってみた → うまくできなかったけど、「チャレンジしたね」と言ってもらえた
- 一人でおつかいに行ってみた → ちょっと緊張したけど、「行けた!」という自信が残った
- ぬりえや折り紙に夢中になって → 作品を褒められて「楽しい」が増えた
こうした「日常の中の“できた”」を少しずつ重ねていくことが、
やがて「自分は大丈夫なんだ」「やってみようかな」という気持ちを育ててくれます。
親が全部を背負わなくても大丈夫です
子どもが不登校になると、親はつい“責任感”でいっぱいになりますよね。
- 「ちゃんとしなきゃ」
- 「自分のせいなんじゃないか」
- 「このままじゃ、この子の将来が…」
でも、大丈夫です。
子どもにとって一番必要なのは、
“正解を出してくれる親”ではなく、“一緒に悩んでくれる大人”なんです。
うまくいかない日があっても、「今日は一緒にゴロゴロしようか」と言える親でいてください。
その関わりこそが、回復の第一歩になります。
家庭の中で「ちいさな学び」を続けていく方法
「じゃあ、まったく勉強しなくていいの?」と不安になる方もいるかもしれません。
もちろん、“その子に合ったやり方で、少しずつ学びのきっかけを作る”ことは大切です。
- 朝の10分だけ一緒に迷路やドリルをやる
- 好きな図鑑を読みながら「へぇ〜」とリアクションしてあげる
- ちょっとしたお料理や買い物も「生活の中の学び」にしてしまう
それに、無理せず始められる家庭学習サービスや、
子どもに合わせて寄り添ってくれるサポート型の教材も増えています。
不登校の子でも取り組みやすい「家庭学習」の選択肢を知っておく
わが家でも、「少しだけでも学びのペースを作りたい」と思って調べた時、
「オンラインでも、無理なく続けられる教材があるんだ」と安心した記憶があります。
不登校の子どもが「勉強って楽しいかも」と感じられるような、
ストレスの少ない教材やサポート体制のある学習サービスを、以下の記事で比較しています。
▶ 不登校の小学生でも安心して使えるオンライン学習サービス3選
└ 無学年式・自宅対応・やさしいサポートがあるサービスを紹介しています。
「できた!」が自然と積み重なると、
子どもは少しずつ、自信を取り戻していけるんです。
まとめ|“その後”は、今の関わりで変わっていく
子どもは、ゆっくりでも、自分の力で育っていく存在です。
そしてその“土台”を支えるのが、いま親がしている毎日の関わりです。
- 焦らず、比べず、子どものペースを信じること
- 一緒に笑って過ごす日があること
- 「今のままでいいよ」と伝えてあげること
それができていれば、きっと“その後”は心配しすぎなくて大丈夫です。
あわせて読みたい関連記事
はじめてこのブログに来てくださった方へ
このブログでは、
子育て・夫婦のライフプラン・保険の見直し・仕事、生活に役立つグッズなど、
暮らしの中で「ちょっと気になってきたこと」を、やさしく整理してお届けしています。
結婚、出産、育児、そしてこれからの備え――
「わが家に必要なこと」を一緒に考えたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
