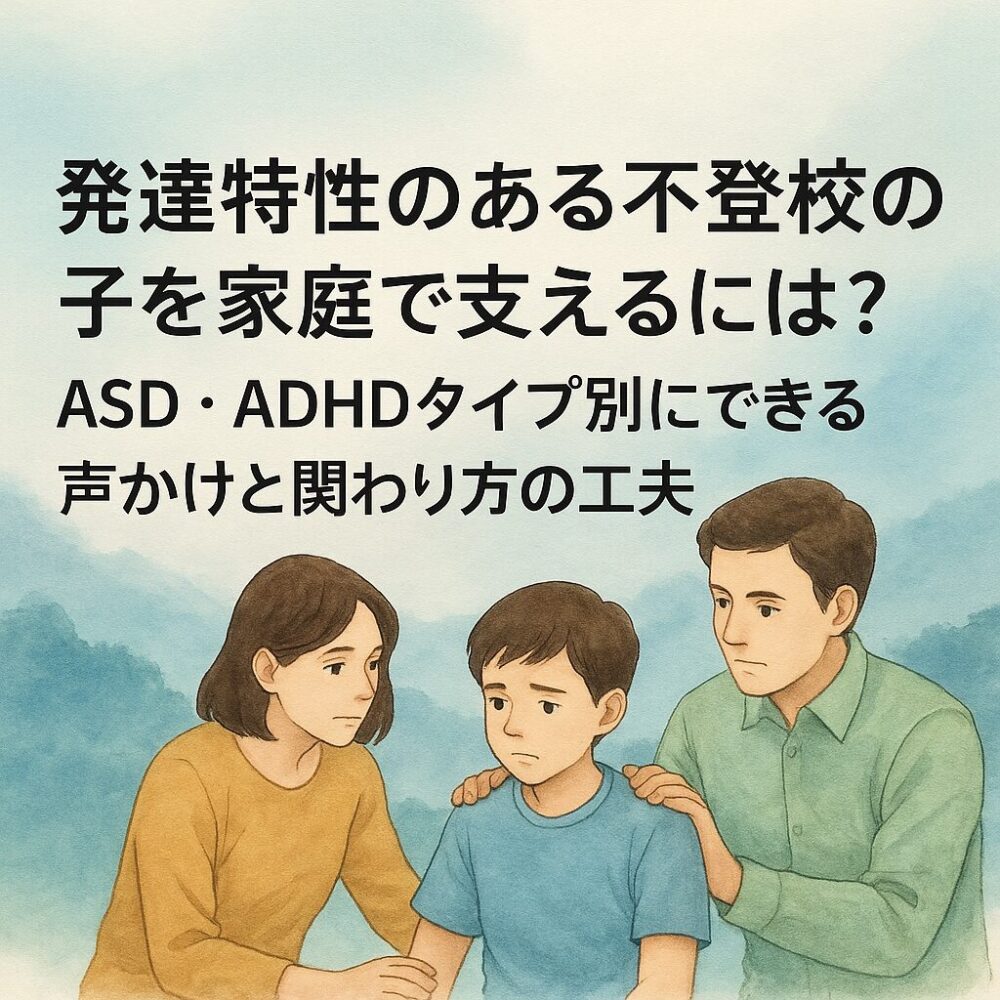
はじめに|“普通の方法”が通じない子どもとの向き合い方
「学校に行けなくなってしまった子ども」。
最初は一時的なことだと思っていました。少し休めば、また戻れるのではないか。きっかけさえあれば……。
でも、数ヶ月が過ぎ、どんどん表情が曇っていく子どもを見ながら、「このままでいいのか」と、心のどこかがずっとザワザワしていました。
夫も心配してはいるものの、どう関わればいいか分からず、一歩引いたまま。
気づけば、検索して、支援先を探して、試しては悩む──そんな日々を私ひとりが背負っていました。
この記事は、そんな家庭で「このままでいいのか?」と不安を抱えている方に向けて書いています。
私は専門職として、発達に凸凹のあるお子さんやご家庭と関わってきました。
でも同時に、私自身も「診断はついていないけれど、ちょっと特性のある子」を育てる親です。
だからこそ、ただの理論ではなく、「現実のしんどさ」「家庭でできること」を丁寧に言葉にしたいと思いました。
この記事はこんな方におすすめです
- 子どもが不登校になり、どう関わればいいか分からず不安な方
- ASDやADHDといった発達特性があるかもしれないと感じている方
- 学校に行けない理由を「甘え」と思われるのがつらい方
- 家庭で何かしてあげたいけど、正解が見えないという方
発達特性のある子が不登校になる背景とは?
発達特性のある子は、見えない「がんばり」を毎日積み重ねています。
- 教室のざわざわした音が気になって集中できない(ASD傾向)
- 黙って座っているのが苦手(ADHD傾向)
- 課題の意図が分からず、他の子のペースに合わせられない
そんな中で、周囲と比べて「できない」と感じたり、先生に注意されたり、友達関係がうまくいかなかったり……。
本人なりに一生懸命がんばっていたけれど、限界を超えたとき、「もう行けない」と体がブレーキをかけてしまうのです。
これは「甘え」でも「逃げ」でもありません。
環境が、その子の特性に合っていなかっただけです。
発達特性のある子どもへの家庭での接し方(ASD・ADHD別)

「うちの子には“普通の関わり方”が通じない」と感じたとき、何をどうすればいいのか悩むのは当然です。
けれど、子どもが示す困った行動の多くは、うまく伝えられない“助けて”のサインかもしれません。
ここでは、ASDとADHDそれぞれの傾向に応じた接し方と、実際に家庭で取り入れられる工夫を紹介します。
「今すぐできる一歩」を見つける手がかりになれば幸いです。
特性に応じた関わり方を知っておくだけで、子どもの不安や拒否感は大きく変わります。
ここでは、ASDとADHDそれぞれの傾向に応じた家庭での対応方法を紹介します。
ASD傾向のある子どもへの家庭での接し方
ASD(自閉スペクトラム症)傾向のある子は、
「突然の予定変更」「曖昧な指示」「音や光の刺激」などに対して強い不安を感じることがあります。
1. 見通しをつける
予測できないことが続くと、ASD傾向のある子は強い不安を抱えやすくなります。
「このあと何をするのか」「どれくらいで終わるのか」をあらかじめ伝えることで、安心して物事に取り組むことができます。
- 「今日やること」を紙に書く
- 時系列で伝える(例:朝→昼→夕方)
- タスクを終えたら“消す”などの視覚的サインを使う
- 声かけ例:「今からプリント3枚やったらおやつだよ」
- 「今日やること」を紙に書く
- 時系列で伝える(例:朝→昼→夕方)
- タスクを終えたら“消す”などの視覚的サインを使う
→ 予定が分かっているだけで、不安感が大きく減ります。
2. 「選ばせる」ことで納得感を育てる
- 「どこで勉強する?リビングと自分の部屋、どっちがいい?」
- 「今はプリントと読書、どちらから始めたい?」
→ 「やらされてる」感を減らし、「自分で選んだ」感覚がやる気につながります。
3. 感覚刺激への配慮
- 音に敏感な子:ヘッドホンや静かな環境を用意
- 光が苦手な子:間接照明やカーテンを工夫
- 安心スペース:布団やテントなど“こもれる場所”を作る
→ 刺激を減らすと、落ち着きやすくなります。
ADHD傾向のある子どもへの家庭での接し方
ADHD(注意欠如・多動性)傾向のある子は、
- 集中が続かない
- 思いつきで行動してしまう
- 落ち着きがないと見られやすい
という特性がありますが、これは「意欲がない」「だらしない」のではありません。
集中のスイッチが独特なだけです。
1. タイマーを使って短時間集中
- 5〜10分で区切る
- 「終わったら少し休憩」などリズムを作る
→ 「できた!」の積み重ねが、自信につながります。
2. 体の動きを活かす
- 音読しながら歩く
- 手元にフィジェットトイ
- 勉強の前にストレッチやジャンプを入れる
→ 「じっと座ること」を求めすぎない方が、逆に集中しやすくなることも。
3. 興味を“入口”にする
- 好きなキャラクターを使って問題を作る
- 好きな分野(電車・生き物・工作など)から学びに繋げる
→ 自分から取り組みたくなる仕掛けづくりが大切です。
学校の集団が合わない場合は「学び方の選択肢」を広げて
感覚過敏やこだわりの強さから、教室の雰囲気が苦手な子もいます。
そんな子には、在宅で自分のペースで学べる環境のほうが安心できることもあります。
わが家では、「オンライン教材を使って学習ペースを保つ」ことが、
子どもの自信回復にもつながりました。
→ 詳しくはこちら:不登校の子どもに家庭でできる学習支援を
共通して大切にしたい「家庭の安心感」
家庭は、子どもにとって“安心できる避難所”であり、再び社会とつながっていくための“充電場所”です。
学校でうまくいかない日があっても、家に戻ればほっとできる。
そんな空気を作ることが、自己肯定感を守るためにとても大切です。
ASDでもADHDでも、診断があってもなくても、
「家庭が“安心できる居場所”になること」が何よりの土台になります。
「できたこと」ではなく、「そのまま」を認める
- 「今日は起きられただけでえらいね」
- 「今日はできなかったね、でも一緒にいられて嬉しいよ」
→ 条件付きの評価ではなく、“その子の存在”を丸ごと受け止める声かけを。
親が無理しすぎない
- 「今日は一緒にゴロゴロしよう」
- 「うまくいかない日もあるよね」
- 「私も今日は疲れちゃったな」と気持ちを言葉にする
→ 親が“がんばらなくていい日”を見せることが、子どもにも「完璧じゃなくていい」という安心感を与えます。
家族全体で“安心ルール”を共有する
安心できる環境は、家族みんなで作っていくものです。
一方的に「こうしてね」と押しつけるのではなく、子ども自身にも“どんなルールがあると落ち着ける?”と問いかけ、一緒に考えることで主体性が育ちます。
- 大声を出さない、否定しない、比較しない
- お互いのペースを尊重する
- 何もしない日があってもOKにする
→ 「ここでは怒られない」「自分のままでいられる」と思える家庭は、子どもにとって回復と再スタートの拠点になります。
- 大声を出さない、否定しない、比較しない
- お互いのペースを尊重する
- 何もしない日があってもOKにする
→ 「ここでは怒られない」「自分のままでいられる」と思える家庭は、子どもにとって回復と再スタートの拠点になります。
- 「今日は一緒にゴロゴロしよう」
- 「うまくいかない日もあるよね」
→ 親自身が自分を許せる姿を見せることが、子どもの安心にもつながります。
専門サポートとつながるという選択肢
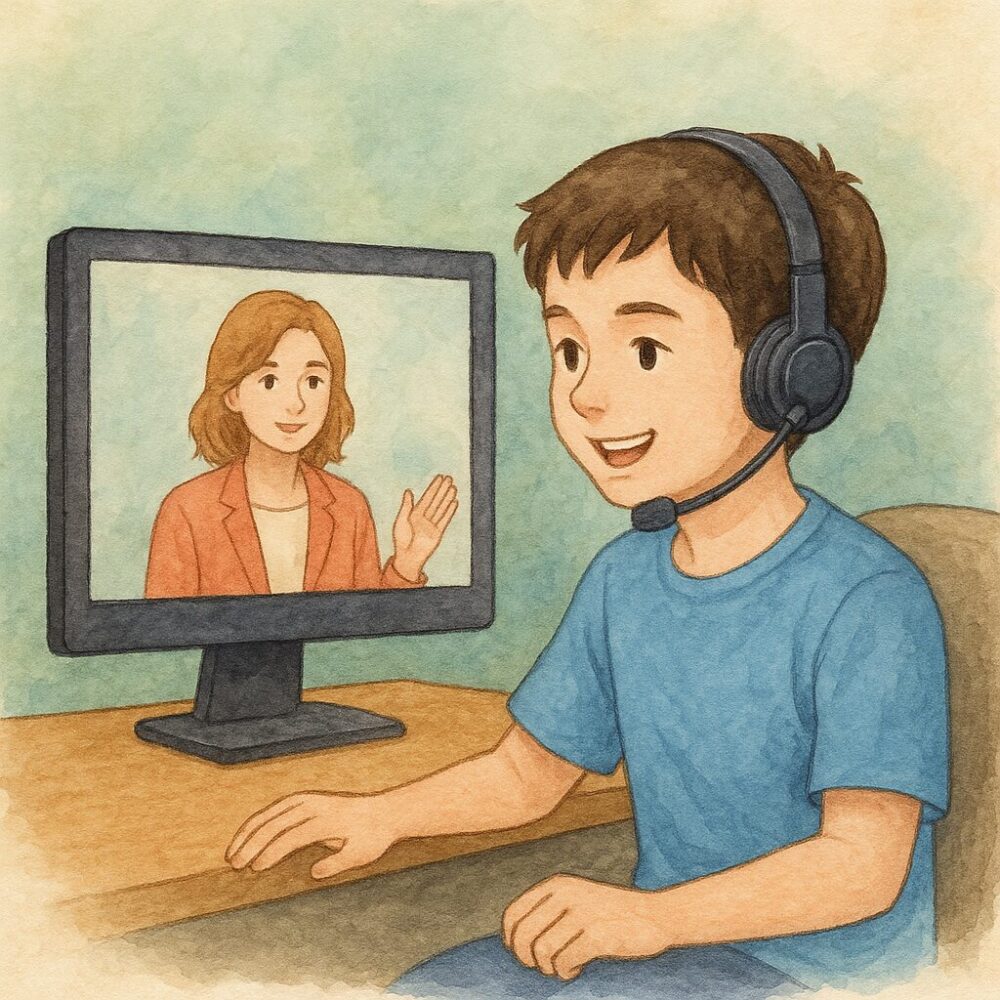
家庭での関わりにも限界を感じることはあります。
そんなときは、無理せず“外の力”を借りてもいいのです。
たとえば「ティントル」のような選択肢
- 不登校専門のオンライン家庭教師
- 発達特性のある子にも対応
- 完全オンラインで在宅OK
- 保護者の相談も可能
「まずは話だけでも聞いてみたい」
そんな気持ちで無料相談から始めるご家庭も増えています。
親自身も「相談できる場所」を持とう
子どもを支えるには、親の心が折れないことも大切です。
「子育ての不安を誰かに聞いてほしい」と感じたときは、
自治体の発達支援センターや子育て相談窓口、NPOなどに頼ってみてください。
悩みを言葉にすることで、自分自身も少しずつ整理がついていくことがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 発達特性があるか分からないけど、この記事を参考にしていいの?
A. はい。診断がなくても、子どもの様子に「ちょっと特性があるかも」と感じていれば、家庭での支援は十分効果があります。
Q. 甘やかしているように見えないか心配です。
A. 安心感や環境調整は「甘やかし」ではなく「支援」です。子どもが再び自分で動き出すための土台づくりになります。
Q. 学校の先生に相談してもいいのでしょうか?
A. もちろんです。ただ、発達特性に理解のある支援先と連携することで、より適切な対応が得られることがあります。
Q. 兄弟姉妹とのバランスが難しいです。
A. 特性のある子への配慮が必要な一方で、兄弟姉妹の気持ちも大切です。時には個別の時間を持つことも意識してみてください。
まとめ|“この子らしい学び方”を信じて支える
不登校も、発達特性も、「特別なこと」ではありません。
子どもたちは、ただ「ちょっと違うやり方」が必要なだけ。
家庭の中から、安心感・自信・そして「またやってみよう」という気持ちが育っていく──そのために、できることを一つずつ。
- 完璧じゃなくていい
- うまくいかない日があってもいい
- あなたの関わりは、ちゃんと届いています
今日の声かけ、今日の“待ってあげる”という選択。
その積み重ねが、子どもにとっての再スタートになります。
あわせて読みたい関連記事
- 不登校の子どもに家庭でできる学習支援を|安心して選べるオンライン学習3社を比較
└ 集団が苦手な子でも、安心して学び続けられる選択肢。家庭で取り入れやすいサービスを紹介しています。 - 不登校の子にかけたい7つの声かけ|親としてできる心の支援とは
└ 学びの前に大切なのは、心の安心。子どもを傷つけずに寄り添う声のかけ方をまとめました。 - 不登校のサインに気づくには?家庭でできる見守りのポイント
└ 「最近なんとなく元気がない…」そんな時に。不登校の兆しに気づくポイントをまとめています。
当ブログのおすすめ記事
- 発達グレー育児と保険|将来への備え方を考える30のヒント[完全ガイド]
- 子どもの「着替え」がうまくできないときにできるサポート方法|作業療法士が家庭で意識してほしいこと
- ライフステージ別 保険の見直しガイド|わが家の体験から学んだ“いま必要な備え”
はじめてこのブログに来てくださった方へ
このブログでは、
子育て・夫婦のライフプラン・保険の見直し・仕事、生活に役立つグッズなど、
暮らしの中で「ちょっと気になってきたこと」を、やさしく整理してお届けしています。
結婚、出産、育児、そしてこれからの備え――
「わが家に必要なこと」を一緒に考えたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
