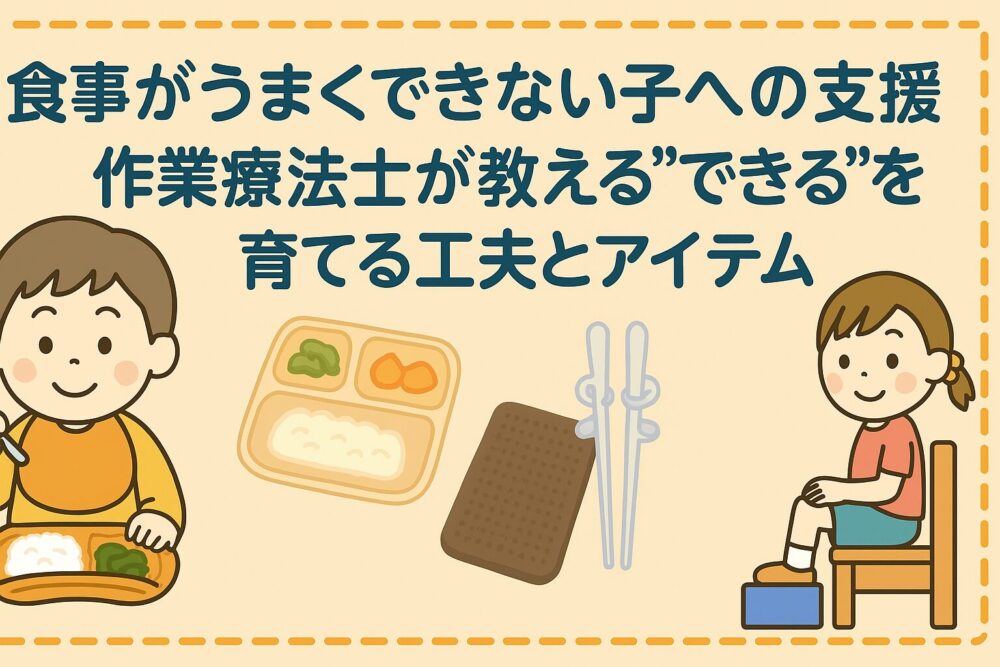
はじめに
「手づかみ食べを嫌がる」「スプーンを使ってもうまくすくえない」「偏食が激しくて…」
食事に関する悩みは、子どもの発達段階によってさまざま。うまく食べられないことで、毎回のごはん時間が“親も子もしんどい”時間になってしまうこともあります。
この記事では、作業療法士の視点から、発達に合った支援の考え方・家庭でできる工夫・おすすめアイテムをまとめました。
こんな人におすすめ
- 子どもの食事中のぐずりや立ち歩きに悩んでいる方
- スプーンやフォークがうまく使えず手づかみばかりの子に困っている方
- 偏食や食感のこだわりが強くて食べさせるのが大変だと感じている方
- 発達に不安があるが、どこに相談すればよいかわからない方
- “できない”を怒るのではなく、“できる”を育てる関わりを知りたい方
食事がうまくできない子に見られるつまずきとは?
- 手先の動きが未熟でスプーンやフォークを上手に使えない
- 食具の持ち方が不安定で食べこぼしが多い
- 食事姿勢が崩れやすく、集中できない
- 感覚過敏やこだわりから偏食・食拒否がある
これらの背景には、手指の発達・感覚の違い・姿勢保持力・生活リズムなど、複数の要素が関わっています。
発達段階別・食事のつまずきと支援ポイント
| 年齢 | よくある様子 | 支援のヒント |
|---|---|---|
| 1歳前後 | 手づかみ開始/食べ物で遊びがち | 食材の形状を工夫/汚してOKの環境を整える |
| 1歳半〜2歳 | スプーンを持ちたがるがうまく使えない | 太く短いスプーンを使って“すくいやすさ”を支援 |
| 2〜3歳 | スプーン・フォークは使えるが箸はまだ | 二股箸やサポート箸を取り入れて成功体験を重ねる |
| 3〜4歳 | 姿勢が崩れやすい/集中が続かない | 足の裏が床につく椅子を使う+時間を区切るなどの工夫 |
作業療法士が伝えたい“家庭でできる支援”の視点
1. 姿勢を整える
- 足がブラブラしていると、手先の動きも不安定に
- 膝・足首が90度になるよう椅子やクッションを調整
2. 食具を変えるだけでも変わる
- 太めのグリップ/軽くて短めのスプーン
- すくいやすい“返しのある皿”や滑り止め付きボウル
3. 食事=楽しい時間にする
- 食べられたらシールを貼る/ミニゲーム化する
- 家族と一緒に「おいしいね」と共感を増やす
→ 無理に「食べさせよう」とすると、子どもは余計に拒否しやすくなります。まずは“できた!”を増やすサポートを。
わが家の体験談|手づかみ→スプーン→箸への試行錯誤

長男は、1歳半ごろからスプーンを持ちたがるものの、うまくすくえず「ぐちゃぐちゃ…」となって毎食ストレス。
試して効果があったのは、“返し”がある小さなお椀+短めスプーンのセット。こぼしにくくなり、自信がついたのか「じぶんで!」の意欲が増えました。
その後は2歳半ごろから、エジソン箸→三点支持箸にステップアップ。スプーン卒業までに約1年かかりましたが、「できた!」の積み重ねが何よりの支えになったと感じています。
食事支援におすすめのサポートアイテム比較表
| アイテム | 特徴 | 向いている子 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| グリップ付きスプーン | 握りやすく滑りにくい | スプーン操作に苦手意識がある子 | 約1000円〜 |
| 返し付き食器 食器が割れるのが心配な方はこちら(吸盤付きワンプレート) | 食材をすくいやすい形状 | こぼしやすい子/手の動きが不安定な子 | 約1,000円〜 |
| 滑り止め付きマット | 食器のズレを防止 | テーブル上で食器が動いてしまう子 | 約800円〜 |
| エジソン箸(サポート箸) | 箸の形に慣れるステップに | 箸にチャレンジしたい時期の子 | 約1,200円〜 |
| 足置き台 or 調整椅子 | 姿勢を安定させる | 姿勢が崩れやすい子 | 約3,000円〜 |
よくある質問(FAQ)
Q. 食事中すぐ立ち上がってしまいます。どうすれば?
→ 椅子が合っていない/集中しづらい可能性があります。時間を区切る・椅子の高さ調整・視覚的見通し(タイマー活用)も有効です。
Q. 偏食が激しくて食べられるものが少ないです。
→ 無理に増やそうとせず、まずは“食べられる形”にアレンジ(例:刻み方・食感・味付け)。小さな成功を積み重ねることが大切です。
Q. 食具をうまく使えないのは発達の問題ですか?
→ 多くは経験不足や道具が合っていないだけのことも。気になる場合は専門家(保健師・療育)へ相談を。
手と口と姿勢の発達がそろって、初めて“食べる”ができる
子どもがスムーズに食事動作を行うには、複数の発達要素がかみ合う必要があります:
- 手指の巧緻性(細かく動かす力):つまむ、持つ、傾けるなど
- 体幹と姿勢保持力:姿勢が安定しないと、手が自由に動かせない
- 口腔機能:咀嚼・嚥下の力、食感の調整力
- 視覚と空間認知:皿の位置、すくう距離感など
これらの力は子どもによって発達のスピードが異なるため、「できない=遅れている」ではなく「今は育ち途中」かどうかを見極めることが大切です。
感覚統合の視点から見る“食べられない理由”
食べ物の“におい”“感触”“見た目”に対して、
- 強い拒否反応を示す子(感覚過敏)
- 気づきにくい・気にしない子(感覚鈍麻)
がいます。
感覚過敏の子は、トマトや納豆の“ねばねば”が耐えられなかったり、味の濃淡に極端に敏感だったりします。
→ 対応としては「無理に食べさせない」「似た感触で慣らす」「見た目からのハードルを下げる」などが効果的です。
支援は“導入→定着→自立”の3ステップで
ステップ1:導入期
- 手づかみ/遊びながら食材に触れる経験
- 楽しい・安心できる環境を整える
ステップ2:定着期
- 食具を使う練習・試行錯誤
- 食事のルール(座って食べる・時間を決める)を覚える
ステップ3:自立期
- スプーン→箸への移行
- 好き嫌いの調整や、必要な量を自分で食べられる力
それぞれの段階で求められる力は違い、子どもの“できている部分”に注目して進めることが重要です。
家族のリアルな声(失敗例と乗り越え方)
ケース1:食べ物を手で触るのを極端に嫌がった娘(1歳9ヶ月)
→ 最初は“手で食べる”経験をスルー。代わりにスポンジや粘土で“感触遊び”をして、手の感覚を育てることから始めた。
→ 3ヶ月後には、自分から“バナナをつかむ”行動が見られた。
ケース2:箸の練習で親がイライラしてしまった息子(3歳半)
→ 毎回の「ちゃんと持って!」の声がけで、親子ともに食事時間が苦痛に。
→ 一旦箸の使用をやめ、スプーンで成功体験を積み直したことで、「やってみたい」に戻ることができた。
療育や行政支援での取り組み
発達が気になる子どもへの支援は、家庭だけでなく地域でも行われています。
療育センターでの取り組み例
- 食具の選び方や使い方の練習(専門職と一緒に)
- 食事場面の観察とアドバイス(個別対応)
保健センターの活用例
- 発達相談や“食べムラ”についての相談窓口
- グループ支援プログラム(親同士の交流も)
→ 「相談していいのかわからない」と迷っているうちに、子どもがつらい状態が長引いてしまうことも。早めの相談が子どもにも親にも優しい選択です。
遊びながら育つ“食べる準備スキル”
日常の“遊び”や“手伝い”も、食事に必要な力を育てるチャンスです。
- おままごと遊び:食材をつかむ・並べる・混ぜるなどの手先の操作
- 粘土遊び・スライム遊び:手の感触に慣れる・力加減を学ぶ
- 料理の手伝い:おにぎりを握る・卵を割るなど、手の使い方+“食”への興味を育てる
“食事=机で食べること”だけではなく、前段階の遊びの中に「準備スキル」をたくさん取り入れていくことで、苦手な子にも自然と“食べる力”が育まれていきます。
兄弟や保育園環境の影響も見逃せない
子どもは“真似”の名人です。保育園や兄弟との食事場面での体験が、大きな刺激となることも。
- 保育園では食べられるのに家では食べない → “みんなと一緒”の安心感や見通しがあるため
- 兄弟ができると急にできるようになる → 「やってみたい」の気持ちが生まれやすい
家庭内でも、「家族で食べる」「お兄ちゃんがやってるからやってみよう」といった“環境からの学び”を活かすことで、自然にステップアップできる子も多いです。
将来に備える“支援と保障”の視点も大切に
食事のつまずきが長く続いたり、他の発達面の不安が出てきた場合、療育や通院が必要になることもあります。
そのときに備えて、家計の中で準備できる“選択肢”を持っておくことは、親の安心につながります。
- 発達がゆっくりな子の通院費・療育費
- 自治体の助成制度と対象外の負担
- 万が一への備えとしての医療保険・共済の活用
実際に「もっと早く備えておけばよかった」と感じる親も多いため、“まだ困っていない今”のうちに情報を集めておくことが、将来の選択肢を広げてくれます。
発達が気になったら、家族でできる備えも大切です
食事のつまずきは、発達のサインとして表れることもあります。
「もしかして少し気になるかも…」と思ったら、早めに相談・準備することが安心につながります。
将来に備えた医療費や療育費への備えとして、「保険の見直し」を選ぶ家庭も増えています。
→ 子育て・発達支援・ライフステージ別に備える|わが家の保険見直しガイド
まとめ|“自分で食べられた!”が明日の一歩につながる
食事は、子どもにとって“自立”を育てる大切な生活スキル。
うまくできない時期があっても、それは「まだ成長途中なだけ」。
できる工夫・楽しい雰囲気・親の“見守り”の姿勢があれば、子どもは必ず一歩ずつ前に進みます。
親も子も笑顔で「おいしいね」が言える時間を、一緒につくっていきましょう。
関連記事・あわせて読みたい
はじめてこのブログに来てくださった方へ
このブログでは、
子育て・夫婦のライフプラン・保険の見直し・仕事、生活に役立つグッズなど、
暮らしの中で「ちょっと気になってきたこと」を、やさしく整理してお届けしています。
結婚、出産、育児、そしてこれからの備え――
「わが家に必要なこと」を一緒に考えたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
