
はじめに

「赤ちゃんが生まれて幸せなはずなのに、気分が沈む…」
「育児のプレッシャーで、何をしても楽しめない…」
「夫婦のすれ違いが増えて、会話が減った…」
赤ちゃんの誕生は喜ばしいことですが、父親の育児うつや母親の産後うつに悩む家庭も少なくありません。
「産後うつは母親がなるもの」と思われがちですが、最近では父親も育児うつになるケースが増加しています。
私たちも、育児のストレスやプレッシャーからお互いに気持ちがすれ違い、何度もぶつかった経験があります。
この記事では、実際に試して効果があった対策や、育児うつ・産後うつのサイン、相談先について詳しく紹介します。
育児うつ・産後うつとは?自分がそうかもしれないと思ったら…
母親の産後うつとは?
出産後のホルモンバランスの変化や育児ストレスが原因で発症し、特に産後1ヶ月〜6ヶ月に多いとされています。
主な症状
- 気分の落ち込み、涙が出る
- 疲れているのに眠れない
- 育児がつらく感じる
- 食欲がなくなる or 過食気味になる
- 夫や家族にイライラしやすい
ポイント 「マタニティブルー」と違い、産後うつは数週間〜数ヶ月続くことがあり、適切なケアが必要です。
父親の育児うつとは?
「育児ストレスや家庭環境の変化」によって、父親も育児うつになることがあります。
主な原因
- 仕事と育児の両立による疲労
- 「父親として頑張らなきゃ」というプレッシャー
- 妻とのコミュニケーション不足
- 自分の時間が取れないストレス
- 子どもとの関わり方が分からず孤独を感じる
よくある症状
- 何をしても楽しくない・意欲がわかない
- 仕事中も育児のことが気になって集中できない
- 夜泣きなどで寝不足が続き、疲れが取れない
- 家庭での居場所がないと感じる
ポイント 母親の産後うつと同じように、父親もうつ症状を自覚しづらく、「自分だけではどうしようもない」と感じると悪化しやすい傾向があります。
チェックリスト|育児うつ・産後うつのサイン
☑️ 何をしても楽しくない、意欲が出ない
☑️ ひどく疲れているのに眠れない
☑️ 育児のことを考えると涙が出る
☑️ パートナーと会話する気力がわかない
☑️ 自分の存在価値が分からなくなることがある
3つ以上当てはまる場合は、「育児うつ」の可能性があります。無理をせず、周囲に頼ったり、専門家に相談することを考えましょう。
実際に試して効果があった育児うつ・産後うつの対策
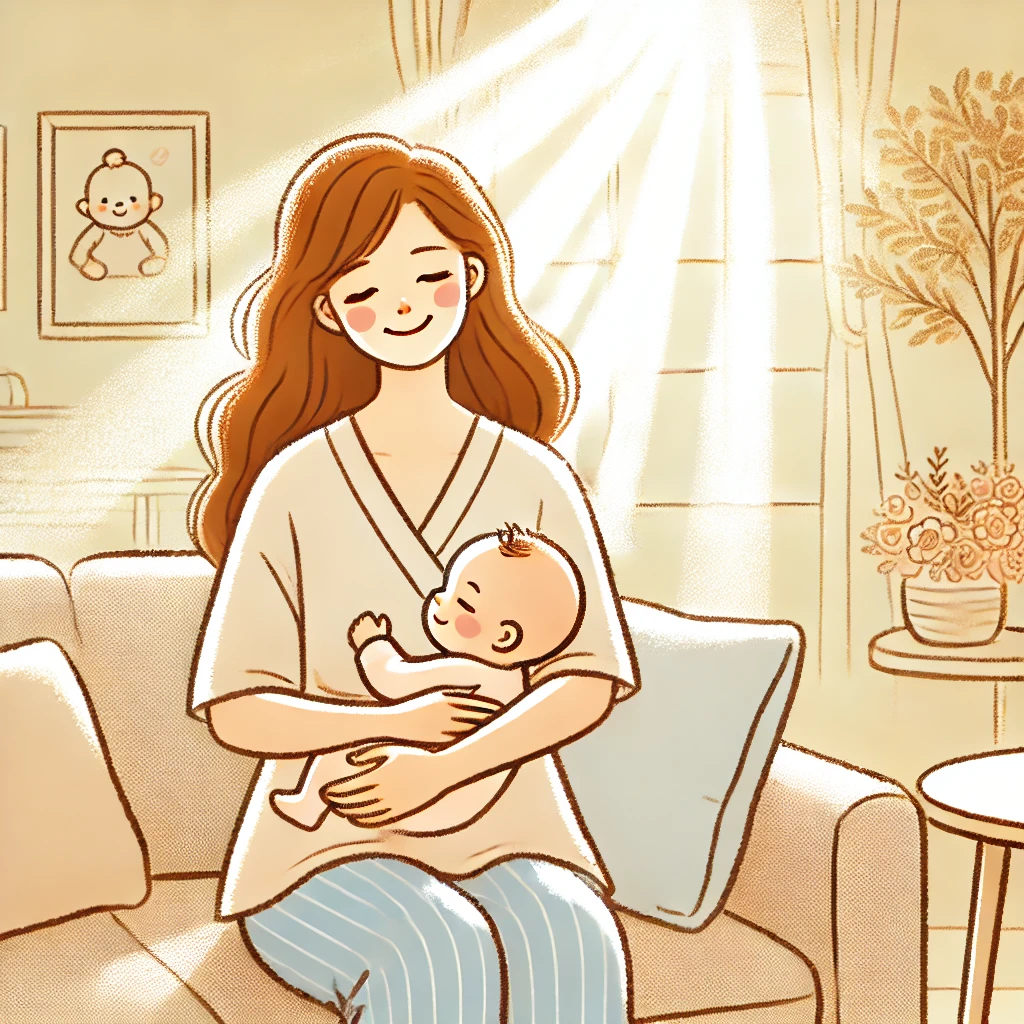
1. 夫婦でのコミュニケーションを増やす
お互いの気持ちを言葉にすることが大切です。
- 「今日、こんなことが大変だった」
- 「○○を手伝ってくれると助かる!」
- 「いつもありがとう!」

「産後うつでイライラしていた時、子供が寝ている時などに夫とゆっくり話す時間を設けるようにしたら少しずつ気持ちが軽くなりました。その後、些細なことでも夫から『何をしたらいいかわからないから教えて』と言われ、コミュニケーションをとる量を増やしたらイライラも緩和されました。」
2. 「完璧な育児」を目指さない
育児は、頑張りすぎると心が疲れてしまいます。
無理をしないポイント
- 家事を手抜きする日を作る(便利グッズや家電を活用)
- 食事は宅配や冷凍食品を活用する
- SNSの「完璧ママ・パパ」と比較しない

「仕事と育児を完璧にこなそうとして、ストレスで爆発寸前だったけど、『手を抜いてもいいんだ』と考えたら楽になりました。」
3. 周囲に頼る&相談する
「自分たちだけで頑張らなきゃ」と思わず、周りのサポートを活用しましょう。
- 産後ケア施設やファミリーサポートを利用する
- 保健師や助産師に相談する(自治体の育児相談窓口など)
- 親や友人に「少しだけ助けて」と頼る
おすすめの相談先
- 市区町村の育児相談窓口(育児支援サービスを案内してくれる)
- 自治体の無料カウンセリング(心理士が相談にのってくれる)
- オンライン育児相談(専門家とチャットや電話で相談可能)
4. 睡眠をしっかり取る
育児うつの予防には、「まとまった睡眠時間を確保すること」が最重要です。
- 夫婦で交代しながら睡眠時間を確保する
- 赤ちゃんのお昼寝中に一緒に寝る
- 夜間授乳をミルクにしてパパとシェアする
ワンポイント 「睡眠不足」が蓄積すると、うつ症状が悪化しやすくなるため、できるだけ休息をとることが大切です。
まとめ|夫婦で協力して育児うつ・産後うつを乗り越えよう!
- 産後うつは、ホルモン変化+育児ストレスが原因で起こる
- 父親も「育児うつ」になる可能性がある
- 夫婦でコミュニケーションを増やすことが予防につながる
- 完璧を目指さず、無理をしないことが大切
- 家族・自治体のサポートを活用し、睡眠時間を確保する
「育児がつらい」「もう限界かも…」と感じたら、一人で抱え込まず、誰かに相談することが重要です。
まずは夫婦で話し合い、小さな工夫から始めてみてください!
