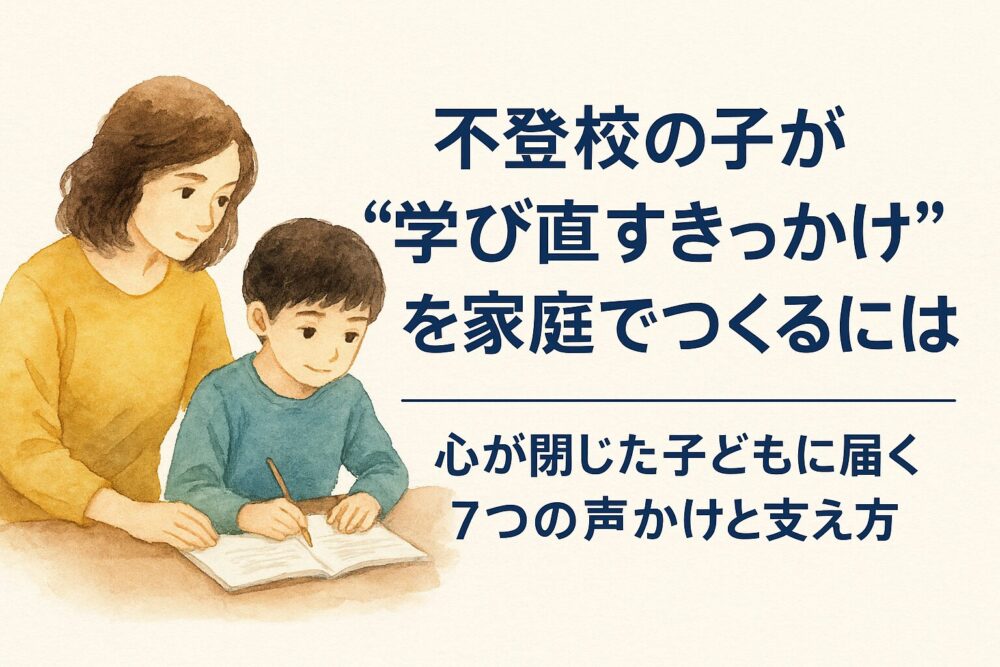
はじめに|「勉強しなさい」が言えなくなったとしたら
私は、不登校の子どもを育てている親ではありません。
でも、「このままでいいのだろうか」と悩む親御さんの声に触れるたびに、
親としての孤独や不安、焦りを想像せずにはいられません。
子どもが学校に行けなくなって数ヶ月。
朝起きても支度はせず、気がつけばスマホやゲームに没頭している。
「勉強はしなくていいの?」と聞きたくなる気持ちはあるけれど、
それを口にすればきっとまた、心の扉を閉ざされてしまう気がする──。
夫も心配している。
だけど、どう関わればいいのか分からないようで、
私が一人で情報を集め、悩みを抱えているような日々。
そんなご家庭の現実が、全国のあちこちにあるのだと思います。
この記事では、不登校の子どもが「また学んでみたい」と思えるように、
家庭のなかでできる7つの声かけとサポート方法、そして心がけたい関わり方を紹介します。
「勉強させる」のではなく、
「一緒に学び直す」ために、今日できる一歩を見つけていきましょう。
わが家の子は、いわゆる“発達障害”の診断は受けていませんが、
音や光に敏感だったり、人と話すだけで疲れてしまうことがあります。
こうした“特性”があると、日常のちょっとした声かけでも伝わり方が変わってきます。
この記事では、そんな子どもに向けた「伝え方の工夫」も含めて紹介しています。
この記事はこんな方におすすめです
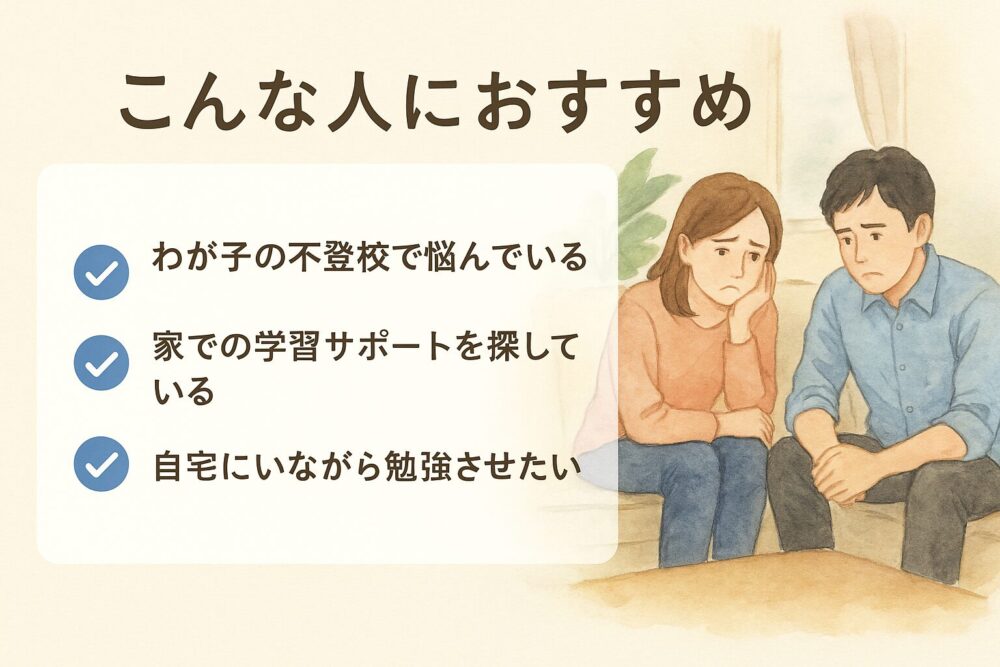
- 子どもが不登校になって半年〜1年以上経ち、学習の遅れが気になっている
- 勉強の話をすると拒否されてしまい、どう声をかければいいか分からない
- 通信教材や塾は試したけど続かなかった
- 夫も心配はしているが、実質的な対応を担っているのは自分
- 家庭の中で、子どもの「やってみようかな」という気持ちを少しでも引き出したい
第1章|なぜ不登校の子は“学び”から遠ざかるのか?
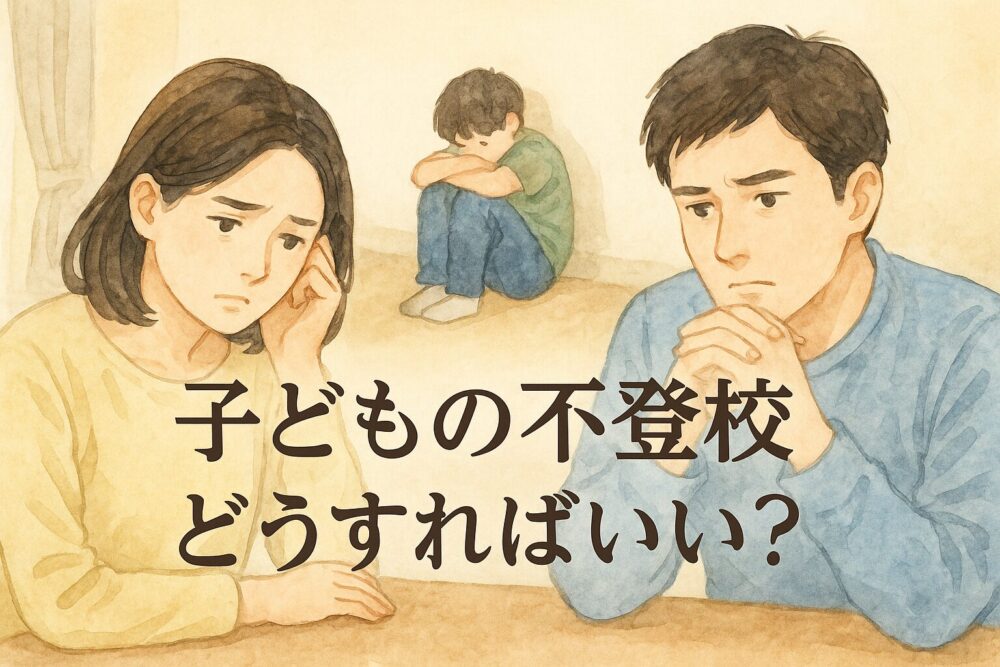
不登校の子どもが勉強を避けるのは、単なる「やる気がない」からではありません。
多くの場合、その背景には“心の傷”や“自信のなさ”、そして“学ぶこと”そのものに対するネガティブな経験が潜んでいます。
学校での「つらい体験」が学びへの拒否感に
- テストの点数で恥をかいた
- 友だちと比べられて劣等感を覚えた
- 授業中に答えられず、先生やクラスメイトに笑われた
こうした出来事が積み重なると、子どもは「学ぶ=傷つく」と感じるようになります。
さらに、「勉強できない自分はダメなんだ」という自己否定の感覚が、
教科書を開く気力さえ奪ってしまうのです。
発達特性が学習のつまずきにつながっているケースも
ADHD(注意欠如・多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達特性を持つ子どもは、
周囲のペースに合わせて授業を受けたり、長時間集中したりすることが苦手です。
でも、学校では「みんなと同じようにできること」が前提で進むため、
「できない自分」を強く意識し、不登校につながることもあります。
その延長線上に、学びそのものを拒否してしまう姿があるのです。
「できない自分を見たくない」から避けている
子どもたちは、本当は学びたいと思っていても、
「またできなかったら」「失敗して笑われたら」と考えて動けなくなっていることがあります。
それは、努力する以前に“心の安全”が必要だというサイン。
学び直しを支える第一歩は、
「やらせる」ことではなく、「怖くないよ、大丈夫だよ」と伝えることから始まります。
第2章|家庭が「再出発の場所」になる理由
子どもが不登校になったとき、「家庭」は文字通り最後の“安全基地”になります。
学校に行けない。社会の中に出られない。
そんなときでも、家庭という空間が「安心できる場所」であることは、子どもにとって大きな支えです。
家庭には「比べられない」「責められない」自由がある
学校ではどうしても「周囲との比較」や「集団での評価」がつきまといます。
でも家庭のなかでは、他人と比べる必要もなければ、失敗を責められることもありません。
「できなかったね。でもまた明日やってみようか」と言える場所。
それが家庭であることは、学び直しの第一歩につながります。
小さな“できた”を積み重ねられる環境に
子どもが「やってみようかな」と思ったとき、家庭ならすぐに試せます。
3分だけプリントをやってみる、図鑑を一緒に見る──
そんな小さなチャレンジを誰にも見られずに、親とだけ共有できる安心感。
「できたね」と言ってもらえることが、次の「やってみよう」につながっていきます。
何もしない時間も“回復の一部”と受け止められる
家庭のなかでは、何もしない時間もまた“その子のペース”です。
何もしていないように見える時期こそ、心を立て直している時期かもしれません。
焦らず、急がず、でも「あなたはひとりじゃない」と伝えることができる場所。
その安心感こそが、「また学んでみようかな」という気持ちの土台になります。
第3章|家庭でできる7つの声かけ・工夫と注意点(+失敗例)
ここでは、家庭で今日から試せる7つの声かけとサポートの工夫を紹介します。
「こう言えばうまくいく」ではなく、「どう伝えるか」「どんな関係を築くか」がポイントです。
①「勉強しなさい」を封印し、「一緒にやってみる?」に変える
失敗例:
「いつまでゲームしてるの?そろそろ勉強しなさい!」
→ 急かされると、子どもはますます“閉じる”。
代替案:
「ちょっとだけ一緒にやってみる?」
「今日は3分だけ机に向かえたらOKってことにしない?」
② 子どもの“好き”を入り口にする
失敗例:
「漢字練習くらいちゃんとやらなきゃダメでしょ」
→ 勉強=強制と感じ、拒否反応。
代替案:
「このゲームの世界って、地理と似てるね」
「漫画のセリフってすごく言葉の勉強になるよ」
③ “できたこと”を見える形で褒める
失敗例:
「ここ、間違ってるよ。やり直して」
→ 間違いにばかり注目されると、自信をなくす。
代替案:
「この1行、自分でできたのすごいね」
「前より字が丁寧になってるよ!」
④「やる気が出ない日」があっても責めない
失敗例:
「昨日はできたのに、なんで今日はやらないの?」
→ 成功がプレッシャーになる。
代替案:
「今日はお休みする日だね」
「またタイミングが来たらやってみようか」
⑤ 学習と“ごほうび”をセットにする
失敗例:
「勉強したらスマホ貸すから」→ 条件付き交換は反発を生みやすい
代替案:
「終わったら、おやつタイムにしよう」
「今日のチャレンジ記念にシール貼ろう」
⑥ 親も一緒に取り組む
失敗例:
「ママは忙しいから自分でやって」
→ 子どもは“ひとりぼっち”と感じてしまう。
代替案:
「ママも横で本読んでるね」
「一緒にタイマーつけて、3分チャレンジしてみようか」
⑦ 毎日でなくても“つながっている”感覚を大切に
失敗例:
「続けなきゃ意味がないよ」→ 継続が義務になると、逆効果。
代替案:
「またやりたくなったら教えてね」
「今日は机に向かわなくても、一緒にいられてよかった」
「がんばろう」という言葉は、一見励ましのように思えますが、不登校の子どもにとってはプレッシャーとなることがあります。「がんばらなくても、あなたはそのままで大丈夫」と伝えることで、子どもが安心感を得られる場合もあります。
このような工夫は、すべて「子どもが自分から動きたくなる空気をつくること」が目的です。
強制ではなく、“子ども自身が選んだ”という感覚が、次の一歩への原動力になります。
第4章|うまくいかないとき、親が抱える“しんどさ”とは?
「子どもを支えたい」と思えば思うほど、うまくいかない現実に落ち込んでしまう。
そんな親御さんの“心のしんどさ”は、外からはなかなか見えません。
子どもには優しく、でも心の中では焦っている
- 「このまま何年も勉強しないままだったらどうしよう」
- 「進学や就職に影響が出るんじゃないか」
- 「周りの子と比べてしまって自己嫌悪になる」
そんなふうに思ってしまうのは、親だからこそ当たり前のことです。
でも、それを誰にも言えずに抱え込んでしまう人も少なくありません。
「私はちゃんとできているのか」と自分を責めてしまう
- 「ほかの家庭はもっと工夫してるのかも」
- 「私がもっと上手に関われていたら…」
そうやって、うまくいかないことの原因を自分のせいにしてしまうことも多いのではないでしょうか。
でも、本当は──
子どもと真剣に向き合おうとしているだけで、もう十分すごいことなんです。
「誰かと一緒に悩んでいい」ことを忘れないで
家庭の中で孤独を感じてしまったときは、「一人で抱えなくていいんだ」と思い出してください。
支援団体や専門家、同じ立場の人とつながることで、
少しずつ「大丈夫かもしれない」と思えるようになる日が来ます。
完璧な親じゃなくていい。
不器用でも、「子どもの力を信じようとしている自分」を、どうか責めないでください。
第5章|家庭+専門サポートという選択肢もある
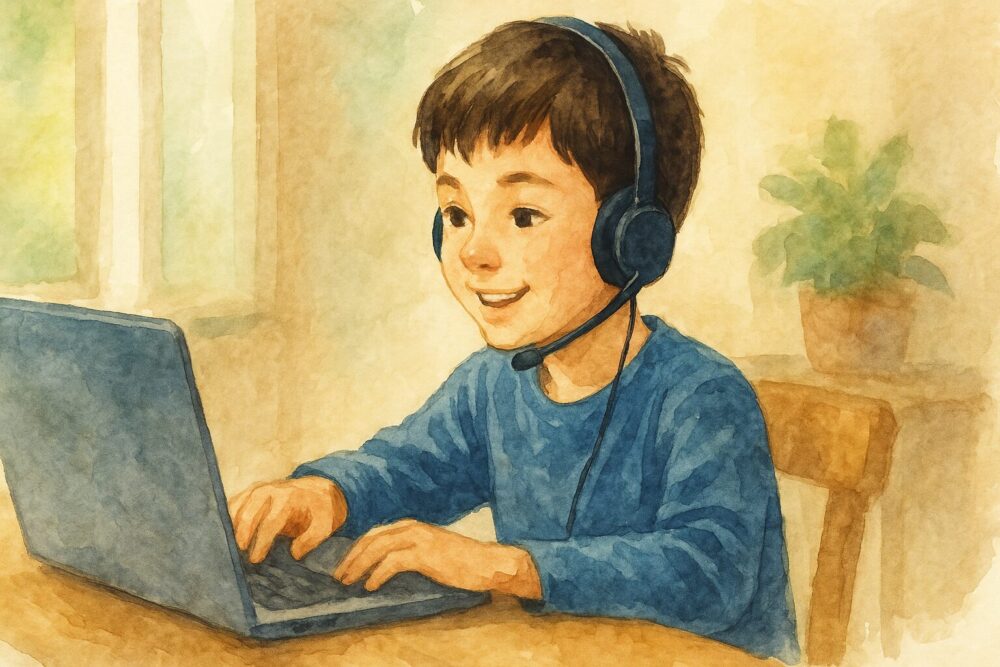
ここまで、家庭でできる関わりや声かけを紹介してきました。
でも、「どうしてもうまくいかない」「限界を感じる」──そんな時もあると思います。
親だけで抱え込まなくていい
子どもが勉強に前向きになれないとき、親として何かしなくてはと思いがちです。
けれど、親が“全部やる”必要はありません。
むしろ、専門のサポートを上手に活用することで、
子どもにも親にも負担が少なくなり、気持ちの余裕が生まれます。
不登校支援に特化したサービスという選択肢
たとえば「ティントル」のようなサービスでは、
不登校や発達特性のある子どもに向けて、専門スタッフが丁寧に対応してくれます。
- 完全オンライン対応で、自宅から受講可能
- 一人ひとりの特性に合わせた個別対応
- 学習支援と並行して、心理的サポートも行ってくれる
- 保護者の相談にも丁寧に応じてくれる体制あり
「家庭でできること」と「外部の力を借りること」は、対立するものではありません。
両方を組み合わせることで、家庭にとって“ちょうどいい支援のかたち”が見えてくるのです。
無料相談からでも十分価値がある
サービスを利用するかどうかに関わらず、
「今の家庭の状況をプロに聞いてもらう」だけでも、視点が変わることがあります。
📌 無料で相談できる窓口から、第一歩を踏み出してみませんか?
「子どもの力を信じてる。でも、ちょっとしんどい。」
そんな時こそ、“外に頼ってもいい”という選択を思い出してください。
FAQ|よくある悩みとその対処法
ここでは、実際に不登校のお子さんを持つ保護者の方から寄せられやすい質問と、
それに対する現実的なアドバイスをまとめました。
Q1. 昼夜逆転の生活が続いています。学習どころではないのですが…
A. まずは生活リズムの改善が優先です。
勉強よりも、「朝起きられた」「お昼に一緒に食事できた」というリズムの再構築が第一歩。
無理に「朝に戻す」よりも、徐々に起きる時間を前倒しするなど、“身体の流れに合わせる”ことが大切です。
Q2. 子どもが全くやる気を見せません。どう接すればいいですか?
A. “やる気がない”ように見えても、その裏には「自信がない」「怖い」という気持ちが隠れています。
「少しだけやってみようか?」という声かけや、一緒に行動するスタイルで“動ける空気”をつくりましょう。
Q3. 勉強を始めても、すぐにイライラして投げ出してしまいます…
A. 成果や正解を急ぎすぎると、失敗がプレッシャーになります。
「できたこと」に焦点をあて、小さな成功を積み重ねることで、少しずつ気持ちが安定していきます。
Q4. 本人が「勉強したい」と言っているのに、継続できません…
A. 意欲が見えているのは前向きな兆しです。
継続のカギは「量」より「習慣化」。
毎日5分でもOK。やったことを可視化(カレンダーやシール)すると自信につながります。
Q5. サポートをお願いするのは“親の怠慢”でしょうか?
A. まったく逆です。
外部の支援を活用するのは、「子どもに合った環境を選ぶ力」があるということ。
“頑張りすぎて壊れてしまう前に頼れる力”も、親としての大切な役割のひとつです。
同じように悩む親御さんの声
「声をかけたいけど、どう言えばいいのか…」と悩んでいるのは、あなただけではありません。
SNSでも「子どもの気持ちを考えるほど、何も言えなくなってしまった」
「良かれと思った言葉で傷つけてしまった」といった声をよく見かけます。
だからこそ、完璧を目指すより、“ちょっとずつ気をつけていく”くらいがちょうどいいのかもしれません。
まとめ|“教える”ではなく“寄り添う”学び直しを
不登校の子どもにとって、「学び直し」はとても繊細なテーマです。
押しつけや比較ではなく、「自分のペースで、もう一度やってみよう」と思える環境こそが必要です。
そして、そのきっかけをつくれる場所が、“家庭”です。
- 小さな声かけひとつ
- 興味のあることを一緒に探す姿勢
- できたことに目を向ける関わり方
それらは、どれも勉強より先に「心を支える学び」です。
もし「一人では難しい」と感じる日があっても大丈夫。
家庭での関わりと、外部の力をバランスよく取り入れていけば、
きっと子どもの“やってみよう”という気持ちが戻ってくる日がきます。
あなたのその思いは、ちゃんと届いています。
焦らなくていい。少しずつで大丈夫です。
あわせて読みたい関連記事
- 不登校の子どもに家庭でできる学習支援を|安心して選べるオンライン学習3社を比較
└ 子どもが「家で学びたい」と感じたときに。家庭でも続けやすい学習スタイルを紹介しています。 - 発達特性のある子への支援|家庭でできる関わりと学びの備え
└ 「学校に行きづらさ」を感じる背景にあるかもしれない特性。その見極め方と関わり方をまとめました。 - 不登校のサインに気づくには?家庭でできる見守りのポイント
└ 「この子、ちょっと様子が違うかも…?」と感じたときに。早めに気づくヒントを紹介しています。
当ブログの人気記事はこちらから
はじめてこのブログに来てくださった方へ
このブログでは、
子育て・夫婦のライフプラン・保険の見直し・仕事、生活に役立つグッズなど、
暮らしの中で「ちょっと気になってきたこと」を、やさしく整理してお届けしています。
結婚、出産、育児、そしてこれからの備え――
「わが家に必要なこと」を一緒に考えたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
