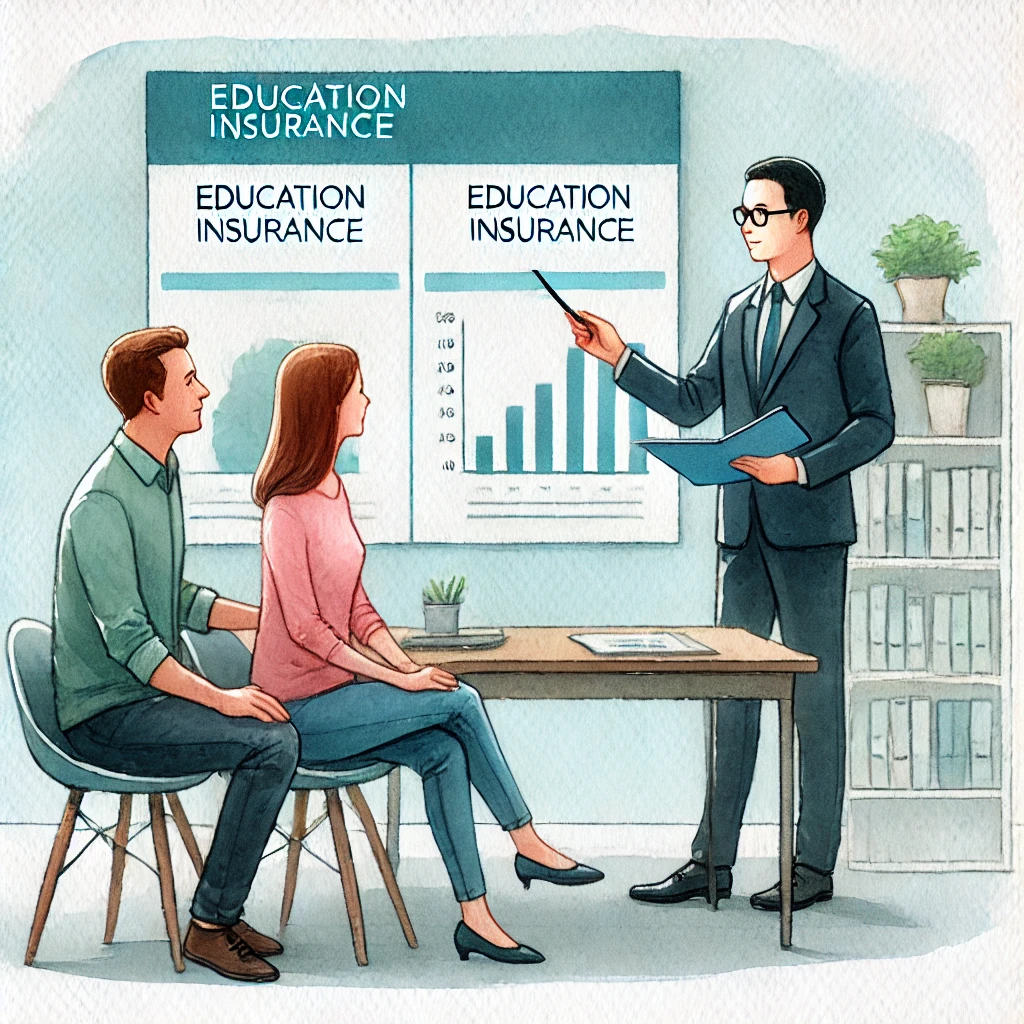
はじめに|「返戻率が高いほどお得」は本当?数字のマジックに騙されないために

「学資保険は返戻率が高いものを選びたい!」
「でも、比較方法がよく分からなくて、結局、返戻率の数字だけ見て決めてしまいそう…」
学資保険選びで最も気になる「返戻率」。 しかし、実は、返戻率の数字だけを見て判断するのは危険です。 高い返戻率の裏に隠された落とし穴があることも…。
この記事では、2025年3月現在の最新情報に基づき、返戻率の基礎知識から、数字のワナ、そして賢い比較方法まで、徹底解説します。
1. 返戻率の基礎知識|知っておきたい3つのポイント
返戻率とは?計算方法は?
返戻率とは、支払った保険料総額に対して、将来受け取る金額(満期保険金や祝い金など)の割合のこと。
計算式:
返戻率(%) = 受け取る総額 ÷ 支払う保険料総額 × 100
「名目返戻率」と「実質返戻率」の違い
- 名目返戻率:単純に支払った金額と受け取る金額で計算
- 実質返戻率:お金の時間価値(インフレなど)を考慮
例:
10年後に100万円を受け取るとします。しかし、もし物価が毎年2%ずつ上昇すると、10年後の100万円は、今の価値で約82万円にしかなりません。
返戻率に影響を与える要素
- 加入年齢:若いほど有利な傾向
- 払込期間:短いほど有利な傾向
- 受取時期:遅いほど有利な傾向(ただし、必要な時期に受け取れるかどうかが重要)
- 保障内容:保障が手厚いほど返戻率は低くなる傾向
- 保険会社:同じような条件でも、保険会社によって返戻率は異なる
2. 返戻率の落とし穴|高い返戻率の裏に隠されたデメリット

保障内容が薄い可能性
返戻率を高く見せるために、死亡保障などが最低限になっている場合がある。
例:
ソニー生命の学資保険(無解約返戻金型)は返戻率が高い一方で、保険料払込期間中の死亡保障が最低限となる傾向がある。他の学資保険と比較し、保障内容や特約を総合的に検討することが重要。
途中解約リスクが高い
- 払込期間が長いプランは、途中で家計状況が変化し、解約せざるを得なくなるリスクがある。
- 途中解約すると、多くの場合、元本割れする。
「早期払込」の注意点
- 保険料を一括で支払うと返戻率は高くなるが、まとまった資金が必要。
- 途中で解約した場合、払い込んだ保険料が全額戻ってこない可能性がある。
- 万が一、保険会社が破綻した場合、払い込んだ保険料が全額保護されないリスクもある。(ただし、生命保険契約者保護機構により、責任準備金の90%までが保護されるため、一部の補償を受けることができます)
インフレを考慮すると?
- 将来の物価上昇により、受け取るお金の実質的な価値が目減りする可能性がある。
👉 【無料】学資保険の比較・相談はこちら

3. 賢い比較方法|返戻率だけじゃない!総合的な判断が大切

「総支払保険料」と「総受取額」で比較する
返戻率だけでなく、実際に支払う金額と受け取る金額を比較する。
例:
A社の学資保険は返戻率105%、B社は103%。しかし、総支払保険料はA社が100万円、B社が95万円の場合、B社の方が総受取額は多くなる可能性がある。例えば、A社の総受取額は105万円(100万円×1.05)、B社は97.85万円(95万円×1.03)となるため、返戻率だけではなく実際の受取額を比較することが重要。
保障内容、特約、付帯サービスもチェック
- 死亡保障、医療保障、払込免除特約など、必要な保障が付いているか確認。
- 子どもの進路相談サービスなど、独自のサービスを提供している保険会社もある。
複数の保険会社で見積もりを取る
- 同じ条件でも、保険会社によって返戻率や保障内容が異なる。
FPなど専門家に相談する
- 中立的な立場から、最適なプラン選びをサポートしてくれる。
- ライフプランに合わせたシミュレーションも可能。
4. まとめ|返戻率だけに惑わされず、総合的に判断しよう
学資保険選びは、返戻率だけでなく、保障内容、払込期間、家計状況などを総合的に考慮することが大切です。
「返戻率が高い=良い学資保険」とは限りません。
数字のワナに惑わされず、本当に自分に合った学資保険を選びましょう。
👉 【無料】学資保険の比較・相談はこちら

